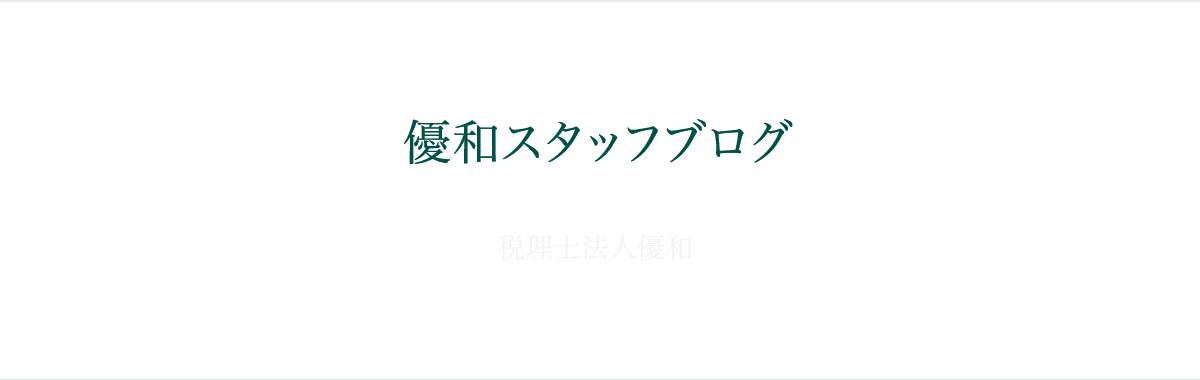
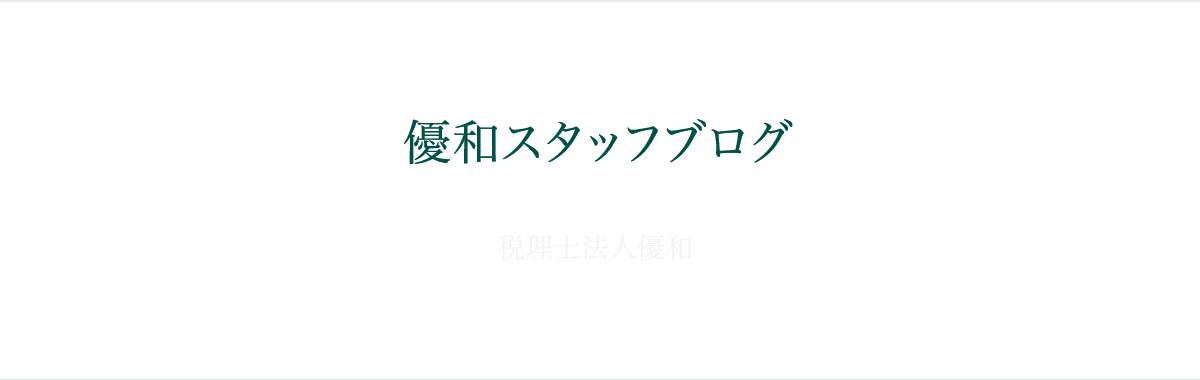
最近は「○○Pay」と名前のついた決済サービスがいっぱい登場するようになりました。
そのPayサービス以外にもクレジットカードや電子マネー等決済方法が多様化して現金を持ち歩かずに支払ができるようになっています。
その中で税金の納付についても国税では既にe-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落により国税を電子納付するダイレクト納付をすることが出来ていますが、2019年10月より地方税についても地方税共通納税システムが開始され国税同様にダイレクト納付が出来るようになりました。
これにより金融機関の窓口等へ出かけることなく手数料無料で全ての都道府県、市区町村へ自宅や職場のパソコンから電子納税が出来るようになります。
10月1日より稼働予定となっておりますが、事前登録実施期間8月19日(月曜)~9月13日(金曜)等の準備が進んでいます。
京都本部 加藤
早起きは苦手です。ギリギリまで寝ているので毎朝、朝食の準備、主人と自分の弁当作り、大量の洗濯、ゴミ出し等…バタバタと時間に追われて出勤、間に合わなかった用事は帰宅してからの持越しになってしまい、また寝るのが遅くなり、翌朝起きれないという悪循環に陥ってしまい、この悪い流れを断ち切ろうと最近少しだけ早起きすることにしました。
朝活!まではできないにしても、せめてやるべき事を終わらせて余裕を持って仕事に出かけられるようにしたいです。朝起きるともうすでに暑いですが、1時間洗濯を干すのが早いとやはり日差しも違い、朝の職場到着時の汗も若干?減ったかも…。
早起きのためには、まず早く寝る!充実した朝の時間が持てるように頑張りたいです。
埼玉本部 高井
先の通常国会にて、マイナンバーカードを健康保険証として利用可能となる法律が成立しました。
平成28年(2016年)以降運用が開始されたマイナンバーカードですが、現在、多くの方にとって影の薄い存在になっているのではないでしょうか?
しかし今後のマイナンバーの運用予定を確認してみると、少しずつ身近になっていくのかもしれません
(今後の運用予定の主なもの)
・健康保険証としての利用
・預貯金口座の付番の義務化
・戸籍情報の連携
・地方公共団体発行の各種カード(図書館カード等)の一元化
・キャッシュカードとしての利用機能
・クレジットカードとしての利用機能 など
将来的にはマイナンバーカードだけで何でもできるワンカード化の促進により、利便性は高くなるものの、各企業や地方公共団体はもちろんですが、各個人のセキュリティ対策も必須となり恐ろしくも感じてしまいます。
一度交付されたマイナンバーは、原則変わることはありません。
今は大丈夫でも将来どんな事が起こるかわかりませんので、マイナンバーの取り扱いには十分注意したいものです。
茨城本部 武田
やっと夏休みらしい暑さになりました
吹奏楽コンクールも始まり、今年は3年連続金賞を目指した夏
練習で悔しくて泣き、それでもサポートしあい高みを目指す部員
助け合う姿って美しいですね
達成した時の嬉し涙
青春を伴奏させてもらった気がしました
まだまだ夏はこれから
体調第一でいきたいと思います
池袋本部 青柳和以
今年の夏は…
涼しくていいけれど、日照時間不足で野菜が高くて堪らないなどと言っていたら、
梅雨明けと同時に猛暑で、暑くて堪らない、もう少し涼しくてもと口にする。
身勝手なものだと思うが、この気候の変動に身体を合わせるのはなかなかに大変で、
呉々も体調管理には気を付けたいものである。
そして。
ここのところの世の中を思う時、
体だけでなく心の調子も整えておきたいなと自らを戒めてもみたくなる。
東京本部 本多
参院選も終わり、まだまだ分からないと言っていた消費増税もほぼ決定になってきました。
消費増税、軽減税率で外食産業が注目されがちですが、一番混乱するのは小規模農家かもしれません。
昨年12月 当税理士法人発行のメルマガ「得する税務・会計情報」でもお伝えしたように、農協に全量おろしている農家などの場合、委託手数料は30%前後掛かりますが、これを差し引いた収入金額で計算してもいいよという制度があります。
言うまでもなく、売り上げ1000万以上から消費税課税事業者になり、納税義務が発生しますから、この制度により、実際の売上は1000万以上でも委託手数料を引くことで課税対象になっていなかった農家も多いと思います。
これが、10月から廃止され、総額での処理が義務付けれらます。
かわりに、簡易課税での仕入控除率はいままでの70%から80%に上がります。 仕入れが10%になるための対策になります。
さて、小規模農家にとっての影響はこれだけではありません。4年後から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
この制度は消費税課税事業者だけが適格領収書発行事業者の番号を取得することができ、この番号の入った領収書を発行することによって購入者は消費税の仕入れ税額控除ができる制度です。
つまり、消費税課税事業者にとっては、消費税を納めていない農家から購入すると、本来引けるはずのものが引けなくなります。購入価格で8%の差があるとなると、販売先が一般消費者ではなく、事業者がメインの場合、たとえ売上げが1000万に満たなくても課税事業者を選択する場合も考えられます。
ただ、農協に委託販売する場合は、インボイスの発行が免除される特例があります。つまり、直接買えば、消費税は引けないが、農協を通した委託販売の場合は消費税を引くことができます。農家からお米を集めているコメ卸業者にとってはびっくりな話ですが。
ただし、農家は無条件委託方式(つまり、売値も、出荷時期も出荷先の条件もつけない)で平均価格(一定期間に出荷した同種・同品質の平均価格)で処理することが条件です。
総額の売上げが1000万前後の小規模農家にとっては、課税事業者になるのか、その場合、簡易課税を選択するのか。また、委託販売を選択するのか、自ら事業者への販売や消費税の関係ない一般消費者だけの販路を選択するのか切実な問題となります。
京都本部 吉原
病院の受付
大きな病院、診察は紹介状がないと診察予約が取れない。
診察の予約を取るのも大変だ。
診察室前
診察の番号が表示されていても、なかなか診察室に入らない人が見受けられる。そのうち名前で呼ばれるか、看護師さんが呼びに来て診察室に入る。年寄りが多いが、時には若者もいる。予約時間は何のためにあるのかがわからなくなる・・・
米つくりにおける中干し
米の作り方。芽出し、種まき、田植え、稲の管理(中干し)、収穫(脱穀)
稲の管理の中の中干しの目的と効果
水を切ることにより生育を抑え、茎数過多を防ぎます。
土の中に酸素を供給し、還元状態で生成される有害成分を除去して、根を活性化させます。
機械作業に適した土の固さを確保します。この時期に一度しっかり干すことで、収穫直前の落水でも容易に田が固くなり機械作業がスムーズに行えます。
人生の中干し反抗期かな
埼玉本部 高橋
先日、地元の保護団体が保護していた子猫を1匹引き取りました。
我が家には6年前に迷いネコとしてやってきて、家族になった先住猫がいます。
常々その子の兄弟が欲しいと思っていたのですが、いろいろな事情により飼うことができずにおりました。
そのいろいろな障害(?)をおおよそ乗切り、じゃあそろそろ本気で兄弟探しをしようか、と思った矢先、先述の猫がやってきました。
あまりのタイミングに縁てあるものだなーと。
生後1か月ちょっとで我が家の一員となりましたが、日々の成長は本当に早くて、約1か月で体重は倍、身長(?)も倍くらいになっています。
先住猫と毎日激しく追いかけっこをしたりお昼寝してたり、我々も生活の中に新たなリズムが生まれた感じで楽しんでいます。

茨城本部 香川
7月に入ってから雨や曇が続いてますね。しばらく太陽が拝めていない気がします。
ですがそんな天気も事務所の移転と同時にあけそうな気配もあり、どちらも少し楽しみにしています。今後共どうぞよろしくお願いいたします。
池袋本部 稲葉
時代が平成から令和へと替わった5月、我が家に新しい家族が増えました。
私と妻は昭和、お姉ちゃんは平成、そして生まれてきた男の子は令和…と、
これで3つの元号生まれが揃いました。
ややこしい、面倒くさいなどと言いながらも、
元号が3つ揃ったコンプリート感を我が家ではワイワイ楽しんでいます。
昭和、平成、そして令和へと、時代の移り変わりとともに、
絶え間なく変化する世の中ですが
どんな時代になろうとも、人間臭さだけは失わないで欲しい、
そんな気持ちでわが子を抱く毎日です。
東京本部 酒井