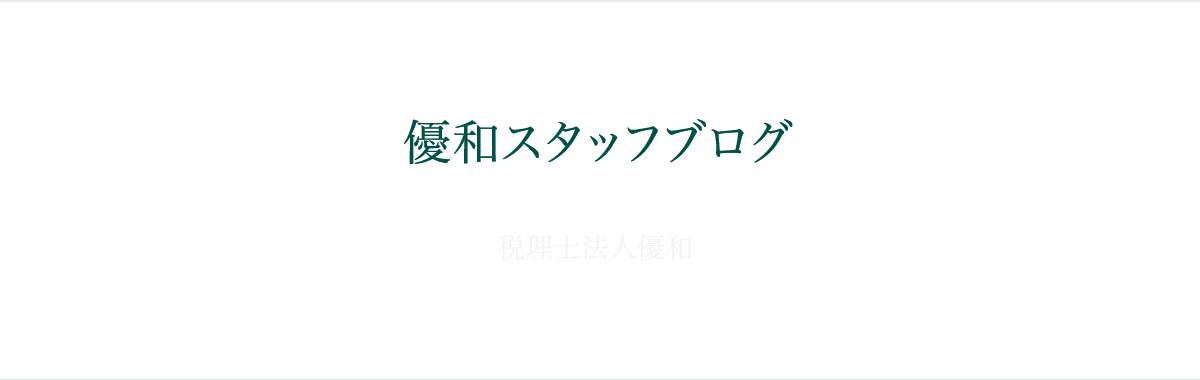
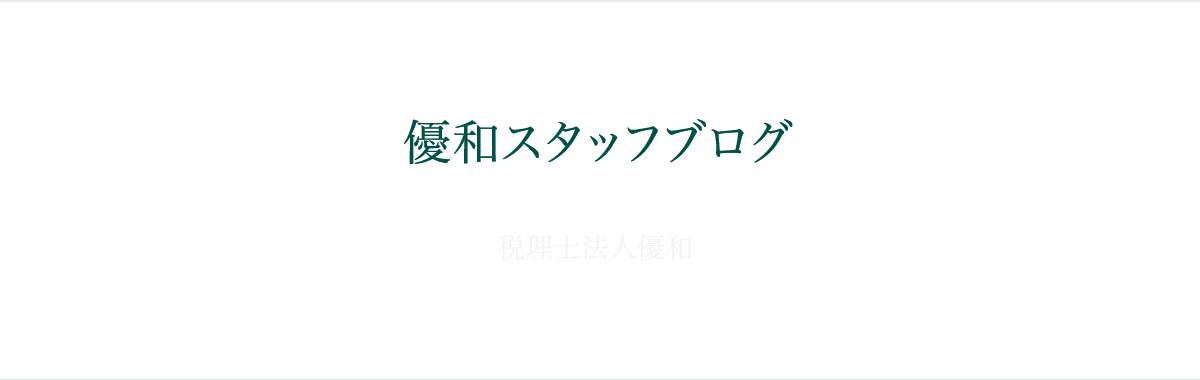
令和6年1月1日以降、相続時精算課税制度が改正されます。
詳細な条件や、制度の説明自体は長くなるためここでは概略を載せます。
いままでの制度は、2,500万円まで贈与税がかかることなく贈与ができたが、以後、超えた贈与には一律で20%の贈与税がかかりました。制度利用後は、すべての贈与が相続発生時に相続財産に含まれる持ち戻しの対象になります。(収めた贈与税は控除されます)
また、暦年贈与と呼ばれる年間110万円の基礎控除枠を利用した贈与ができなくなることもあり、制度自体の利用は伸び悩みました。
今回、相続税において、今まで相続発生時から3年前までの贈与が相続に含まれるという持ち戻し期間が7年に延長されます。
それに合わせて、制度の利用を促進する意味でも相続時精算課税制度に、利用後も年間110万円の基礎控除が新設されました。しかも、基礎控除内での贈与は相続発生時に持ち戻しの対象外になります。
今まで躊躇していた理由でもある暦年贈与が事実上、使えることと、その部分が持ち戻しの対象外になることもあり、利用を検討されている方が増えています。
もちろん、今までと同じく、制度利用にはメリット・デメリットがあり、安易に利用するのは注意が必要です。今回の改正のように、後からの制度改正もリスクになります。
財産が多額に上る人にとっては、贈与税を納めながら、毎年まとまった額を贈与しつづけた方がメリットが大きい場合もありますし、制度を利用して贈与した土地には小規模宅地が使えない、物納の対象にできないなどのデメリットも変わらず残ります。
ただ、夫婦ともにある程度の財産がある場合など、片方だけが制度を利用することで父親は暦年贈与110万、母親は制度を利用した110万といった方法で年間220万を子供に無税で贈与することも考えられます。
実際に新し制度が始まればいろいろな事例が出てくると思われます。
税理士法人優和では、皆さまの税務に関するお悩みを少しでも解消できるお手伝いを行っています。お困りの方はぜひお気軽にご相談下さいませ。
京都本部 吉原
税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。
この少額特例は、税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。
適用対象期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間となります。
この期間内に行う課税仕入れが適用対象となりますので、たとえ課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりませんので、仕入税額控除を受けるためには、原則として、インボイスと一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となります。
少額特例は税込1万円未満の課税仕入れが適用対象となります。
「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る税込み金額が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。
したがって、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)には、少額特例の対象とはなりません。
新しい制度が始まったばかりで、不安を抱えている納税者の方も少なくないと思います。判断に迷うなどお困りの際には、税理士法人優和 京都本部までお気軽にお問い合わせください。
京都本部 良川
「令和5年版高齢社会白書」(内閣府)によると、65歳以上の高齢者人口は3558万人で、令和47年(2065年)には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になることが推計されています。
帝国データバンクのの調査によれば、社長の平均年齢は63.7歳となり、過去最高を更新しています。企業においても経営者の平均年齢は年々上昇傾向で推移しており、円滑な事業承継が求められています。
身内等に後継者がいれば問題はありませんが、「後継者が不在」「後継者はいるが継ぎたくない」といったケースの場合、企業としては「廃業」もしくは「第三者承継(M&A)」を検討しなければなりません。
中小企業を廃業から救い、事業承継の問題解決を促すために、事業承継時の贈与税・相続税の納税が猶予になる事業承継税制(特例措置)が設けられています。
非上場の株式等を先代経営者から後継者が相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除され、実質負担額が0になります。
この制度の適用を受けるためには、認定支援機関の指導・助言が必要になります。
税理士法人優和 京都本部では、認定支援機関として事業承継のご支援にも取り組んでおります。
事業承継対策でお悩みの方、「事業承継税制を活用したいが、顧問税理士事務所が認定支援機関でない」とお困りの方は、ぜひお気軽に税理士法人優和 京都本部までご相談ください。
京都本部 盛田
インボイスの適用が近づいたことで、不動産賃貸業の方も
消費税について関心が高まっています。
インボイスだけに注意が行きがちですが、意外に見落とされているのが
別途請求している水道光熱費の取り扱いになります。
基本的にテナントから賃料とは別に徴収している電気料金等は消費税法基本通達10-1-14において、建物等の資産の貸し付けにかかる対価に含まれるとされ課税売上になります。
ただし、テナントごとに区分された電気メーターの検針結果をもとに、単にオーナーが一時預かりしているだけのような場合は、預かり処理をすることを条件に消費税の対象外にすることが認められています。
さて、一番間違いがみられるのが、簡易課税の場合の扱いです。
不動産賃貸は事業区分第六種になりますが、電気料金はどうでしょうか。
オーナーが電力会社から購入した電気を品質、形状を変更しないままテナントに
売っているとなるため、別途請求としている場合、第二種事業に該当すると考えられます。
意外に水道光熱費は大きくなるので注意したいところです。
ちなみに、今回はテナント賃貸を参考にしましたが
アパート等の場合、オーナーが課税事業者かつ簡易課税であれば、トータルで
検討したいところです。
つまり、大体一定の水道光熱費になっている場合、家賃に含めて請求すれば
全体が非課税になりますが、別途で請求していれば課税売上となります。
簡易課税は課税売上に対して計算されるので、先ほどの第二種事業とあわせて
検討するとより、消費税を節税できます。
不動産賃貸もインボイス制度もいろいろなケースがあります。
ご相談は税理士法人優和へ。
2023年10月よりインボイス制度の運用が始まります。
制度が始まると、請求書の発行や消費税の取り扱い等に変更が生じるため、請求書発行や会計決済等のシステムを制度に対応したものへ変える必要があります。
これを機にPC・レジ・券売機等のハードウェアの導入や買い替えを検討されている事業者様も多いのではないでしょうか。
インボイス制度への対応を目的としたツールの導入は、IT導入補助金「デジタル化基盤導入類枠」の申請対象となります。
デジタル化基盤導入枠は、中小企業・小規模事業者等が導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。
補助対象となる経費は、会計・受発注・決済・ECのうち、1つ以上の機能を有するソフトウェアの購入費、クラウドサービス利用料、導入にかかった費用、そしてソフトウェアやクラウドサービス等を使用するハードウェアの購入費の4つです。
2022年の補助金と比較すると、ITツール導入補助額の下限が撤廃されたため、少額のツール導入に対しても補助金の申請ができるようになりました。
今後ITツールやハードウェアの購入を検討されている方は、補助金の活用ができないかどうかご確認ください。
インボイス制度やその他税務についてお困りの際は、税理士法人優和 京都本部までご相談ください。
2022年度の税収が71兆円台となり、3年連続で過去最高を更新したそうです。
そんな中、賃上げ促進税制も令和4年度税制改正で、以前に比べ要件が簡素化され、
かつ控除率も引き上げられ企業の賃上げを後押しする形となっています。
【通常要件】
用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合
→ 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
【上乗せ要件①】
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合
→ 税額控除率を15%上乗せ
【上乗せ要件②】
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
→ 税額控除率を10%上乗せ
上乗せ要件①だけを満たす場合→30%を税額控除
上乗せ要件②だけを満たす場合→25%を税額控除
上乗せ要件①②ともに満たす場合→40%を税額控除
※ただし、法人税額又は所得税額の20%が上限となります。
例えば当期の法人税額が700万円で、
給与等の支給増加額が500万円(1億→1.05億、5%増加)の場合
→ 500万円×30%=150万円
ただし、法人税額の20%が上限なので、700万円×20%=140万円が税額控除されます。
本制度の適用については、事前の届出等は一切必要ありません。
業績が好調な事業者の方は、昇給や賞与支給などで本制度を有効活用されてはいかがでしょうか。
京都本部 良川
中小企業者等が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において
国内雇用者に対し給与等を支給する場合、
その事業年度に中小企業者等の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を
控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、
その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。
所得拡大促進税制の令和4年度税制改正においては要件の見直しが行われ、
経営力向上要件は廃止となりましたが、最大40%の加算措置の適用が可能となり、
税額控除額上乗せ要件の2つが見直されています。
所得拡大促進税制は、令和3年度の改正により、雇用を守る制度に変更となり、
その後令和4年度の改正では税額控除額の見直しが行われています。
所得拡大促進税制は、法人税が減額される税制ですが、適用を受けるためには比較作業等が必要となり、
控除上乗せを利用する場合にはさらに必要書類等もあります。
また、令和5年3月31日までの適用期限が1年延長され、令和6年3月31日までとなりました。
手続きには時間を要するため、ご自身でされるには少しハードルの高い制度となっております。
そのため、適用を受けたいとお考えの際は早めに税理士に相談、サポートの依頼をおすすめします。
この制度に限らず税制面の制度にお困りの方は是非当税理士法人までお問い合わせください。
京都本部 櫻井
1)概要
スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払い(〇〇ペイ)を選択してすべての税目について納付できる手続きのことです。なお、国税スマートフォン決済専用サイトは、国税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税のスマホアプリ納付専用の外部サイトのことです。
(2)利用開始予定日
令和4年12月1日(木)から利用可能です。
(3)利用可能なPay払い
PayPay、d払い、auPAY、LINEPay、メルカリPay、amazon pay
(4)納付手続
①事前準備 納付する税目や金額がわかる資料(確定申告書等)と、利用するスマートフォン
②専用サイトへアクセス
インターネットの利用が可能なスマートフォンから、納付受託者が運営する国税スマートフォン決済専用サイトへアクセスします。アクセス方法としては、e-Tax又は国税庁ホームページからの2つの方法があります。
・e-Tax:e-Taxを利用して申告書・源泉所得税徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後、メッセージボックスに格納される受信通知からアクセスします。
・国税庁ホームページ:国税庁ホームページに表示されている国税スマートフォン決済専用サイトからアクセスします。
③専用サイトで納付情報を入力
詳細な手続きについては、令和4年12月1日(木)に国税庁のホームページにて掲載予定です。
(5)メリット・デメリット
①メリット
・クレジットカードでの納付ですと決済手数料がかかりますが、Pay払いの場合には手数料を国が負担するためかかりません。
・コンビニ払いなら決済手数料はかからないものの、納付用のQRコードを印刷する必要がありますが、Pay払いの場合には不要で、24時間いつでも時間や場所を選ばずに納付が可能です。
②デメリット
・決済上限額が30万円(Pay払いで利用上限を設定している場合はその上限額)となります。
・Pay払いそれぞれのアカウント残高から納付することとなるため、残高の準備が必要となります。
・領収証の発行はできません。
・Pay払いによってはポイントが付与されるものとそうでないものがあります。
埼玉本部 秋元
ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻は以前に比べ報道が少なくなったように感じますが、まだまだ続いています。
そしてウクライナ支援のため在日ウクライナ大使館に寄せられた寄付金が50億円を上回り人道支援に生かしていく方針が示されました。
私の担当している顧問先様でも直接、在日ウクライナ大使館に寄付をされていました。
その顧問先様は純粋な支援目的だったため、その寄付が税制上優遇されるかどうかは度外視でしたが、
私は立場上それについての税制上優遇がないかと検討をします。
寄付金控除等について、
「個人が国や地方公共団体、公益社団法人等が募集する寄附金で財務大臣が指定したもの、独立行政法人や公益社団法人等の主たる目的である業務、
認定NPO法人の特定非営利活動への寄附金(特定寄附金)を支出した場合、寄附金控除という所得控除を適用できることが規定されています」
が、ここでいう国とは「日本」のことで外国は含まれません。
結果、その寄付について税制上優遇は受けられませんでした。
税制上優遇を受けつつ寄付をしたい場合は日本赤十字社や日本ユニセフ協会など
ウクライナ支援活動を行っている団体に寄附をすることで特定寄附金に該当し、控除が受けられます。
また、ふるさと納税制度を通じてウクライナを支援することができますが、私個人としてはこれには少し違和感を覚えます。
今回多くの方がされた支援の気持ちを金銭に変えて在日ウクライナ大使館の窓口から直接ウクライナに届けたいという考えはよくわかります。
もし、寄付を受ける方と寄付をされる方、双方効果的な寄付をお考えの方は税理士法人優和までご相談下さい。
京都本部 加藤
保険といえば、生命保険や傷害保険などが一般的ですが、あまり知られていないものに少額短期保険(ミニ保険)と呼ばれる商品があり、人気となっております。この少額短期保険は、2006年の保険業法の改正で誕生したものですが、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間が1年(傷害保険の分野2年)以内の保険で、保障性商品の引受けのみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられております。
少額短期保険、いわゆる「ミニ保険」は2005年5月2日公布による「保険業法等の一部を改正する法律」で制度が導入され、2006年4月1日から施行されました。「少額短期保険事業者」は、金融庁財務局に5月27日現在で115事業者が登録されておりますが、この少額短期保険事業者は、通常の保険会社とは異なり、様々な商品を販売することができ、生命保険会社が販売する生命保険も取り扱えることとなっております。
しかし、この「少額短期保険事業者」との契約による生命保険料は、税務上生命保険料控除の対象とはならないので注意が必要です。というのも、所得税法上、生命保険料控除の対象となるには、保険業法2条3項の生命保険会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることが要件の一つとなっておりますが、少額短期保険業者との契約はこの要件に該当しないため、生命保険料控除は適用されないのです。
少額短期保険事業者は、保険業法2条17・18項で規定されており、保険業法上、生命保険会社とは別の保険業として区分されているので、たとえ死亡保障のために交わした生命保険契約であっても、少額短期保険事業者との保険契約は、税務上、控除の対象とはならないのです。もちろん、年末調整や確定申告時にも、少額短期保険事業者からは「生命保険料控除証明書」は交付されません。
少額短期保険のメリットは、既存の生損保にない商品が発売されており、保険料は掛捨てタイプなので一般的に割安なものが多いこと。一番多いのは生保分野では医療保険などで、損保分野では賃貸用の家財の火災保険があります。また、ペット保険の大半は少額短期保険業者が取り扱っております。デメリットは、支払った保険料が保険料控除の対象とならないことを始め、広告宣伝などを行わないため、知名度が低くあまり知られていないことです。
埼玉本部 秋元