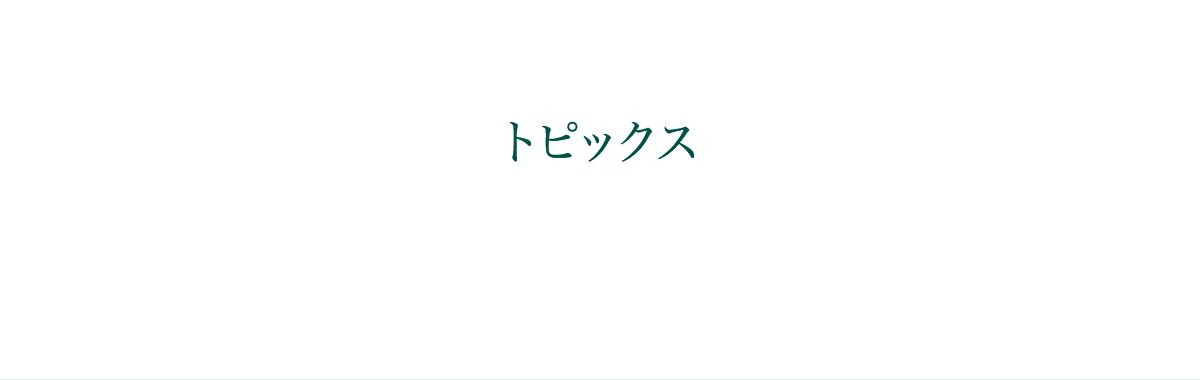
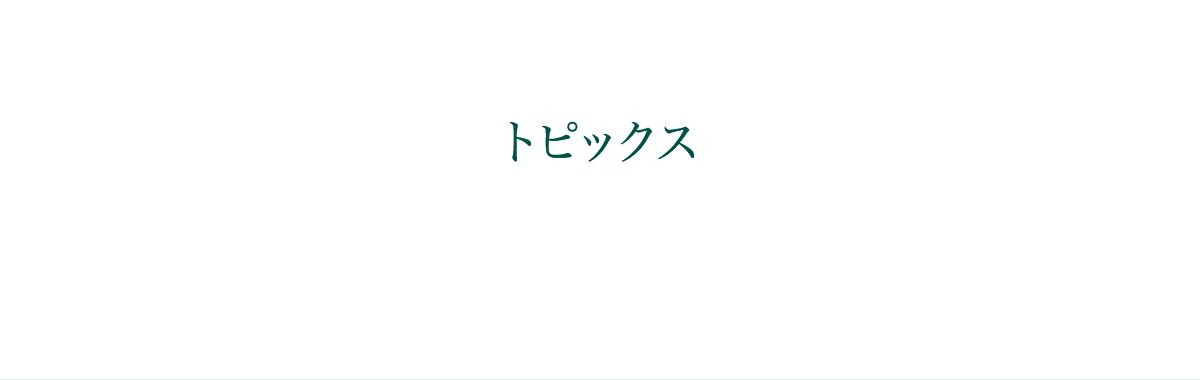
インバウンド需要も高まり、民泊など賃料収入を得る目的で不動産を購入する方も増えてきました。いわゆるオーナーチェンジで事業参入するケースもあり、その際に頭を悩ませるのが、購入後の修繕費の扱いです。
中古の賃貸アパートを購入し、その直後に外壁塗装工事を行った場合、①建物の維持管理に必要な周期的な経費なので修繕費、②資産を事業の用に供するために直接要した費用の額なので取得価額に含める、の2つの処理が考えられます。
その建物だけに注目すると、購入する前も事業の用に供されており、これについて支出する修繕費については、資本的支出もしくは修繕費の判定区分によるのではないかと思われます。ただ、法人税の昔の通達にはなりますが、以下のようなものがありました。
(旧法人税基本通達235)
次に掲げるようなことのために支出した金額は、令第132条の規定を適用して資本的支出と修繕費の区分計算をしないで、その全額を修繕費と認めるものとする。
ただし、自己の使用に供する等のため他から購入した固定資産について支出した金額又は現に使用していなかった資産について新たに使用するために支出した金額は、修繕費としない。
(1)家屋又は壁の塗替
(2)家屋の床のき損部分の取替
(3)家屋の畳の表替
(4)き損した瓦の取替
(5)き損したガラスの取替又は障子、襖の張替
(6)ベルトの取替
(7)自動車のタイヤの取替
この旧通達は例えば、中古の建物を購入してこれについて修繕を行って使用する場合の修繕費は、その建物にとっては修繕費であっても、購入した法人の立場から考えれば、その建物に修繕を行って初めて事業の用に供しうる建物としての機能を発揮しうるものですから、修繕費とすることはできず、建物の取得価額に算入すべきと整理したものと解されます。
この取扱によると、今回の外壁塗装工事は②の処理となり、アパートの取得原価に含まれることになります。
以上のように、通常の税務処理とは異なる結果になることもありますので、大きな設備投資の際には是非事前に税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 木村
◆ネットジャーナル
中国:25年7~9月期の成長率予測
~前期から一段と減速。
政策効果の息切れにより内需が悪化
米個人所得・消費支出(25年8月)
~実質個人消費(前月比)は+0.4%と前月に一致
したほか、市場予想を上回り、堅調な消費を確認
◆経営TOPICS
サービス産業動態統計調査
2025年(令和7年)7月分(速報)
◆経営情報レポート
変化の激しい時代に生き残る!
福利厚生による組織風土の改革方法
◆経営データベース
資金繰り表作成のポイント
資金繰りの考え方
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/k939.pdf
◆医療情報ヘッドライン
24年度に診療所の利益率が大幅悪化
赤字割合は約4割に 日医調査
特定行為制度のWGが初会合
効果的・効率的な研修へと見直し
◆週刊 医療情報
救急搬送多いと経営悪化の傾向、
厚労省集計
◆経営TOPICS
病院報告
(令和7年6月分概数)
◆経営情報レポート
歯科医院を取り巻く経営環境から考える
差別化戦略の策定ポイント
◆経営データベース
退職金制度の見直し・改訂
ポイント制退職金制度の形態
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/i888.pdf
◆したたかに立ち回る非製造業
◆私どもは仏心の中に生まれ、生き、息を引き取る
◆転換期の東南アジア経済
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/656c152f1434e161cdca08a061a6032e.pdf
先日(8月29日)に、国税庁が「令和7年分の年末調整のしかた」を公表しました。今年は、12月1日より施行される所得税の基礎控除や給与所得等の見直し、特定親族特別控除の創設などがあるため、これについて改めて確認していきたいと思います。
(1)所得税の基礎控除の見直し等特定親族特別控除を年調で適用
令和7年12月1日から基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件等が改正されます。これらの改正により、会社は新たに扶養控除等の対象となった扶養親族等がいないか従業員に確認する必要があります。そのため、新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる場合には、従業員等からその旨を記載した扶養控除等申告書の提出を受ける必要あります。
19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の親族(特定親族)がいる場合には、その従業員等は新たに「特定親族特別控除」の適用を受けることができます。そのため、年末調整では特定親族特別控除の適用を受ける従業員等から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」(基礎控除申告書等との兼用様式)の提出を受けることが必要となります。
この場合、改正後の基礎控除等や改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づき年末調整の計算を行うことになるので注意が必要です。
(2)年末残高調書を用いた方式(調書方式)による住宅借入金等特別控除について
これについては、令和7年分の年末調整から、調書方式で住宅ローンを適用する従業員等への対応が必要となります。調書方式とは、金融機関等が税務署に提供した情報に基づき、国税当局から従業員等本人に住宅借入金等の年末残高情報を提供する方式になります。調書方式に対応した金融機関に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出した従業員等は、調書方式で住宅ローン控除を適用することになります。
調書方式の場合には、従業員等が会社に提出する「給与所得者の住宅借入金等の特別控除申告書兼年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」に、「住宅取得資金に係わる借入金の年末残高等証明書」の添付が不要となります。
令和7年度の年末調整に関しては、上記の様に様々な改正点があります。ご不明な点は税理士法人優和までお問い合わせください。
東京本部 佐藤芳明
◆医療情報ヘッドライン
医療事故調査制度の関係団体ヒアリング
センターの報告推奨も未実施が3割以上
電子カルテ「導入不可能」が54.2%
日本医師会「義務化は地域医療崩壊に」
◆週刊 医療情報
「経済・物価動向」
予算編成過程で反映へ
◆経営TOPICS
医療施設動態調査
(令和7年5月末概数)
◆経営情報レポート
法改正・制度改正からみる
スタッフ雇用条件の変更点
◆経営データベース
退職金支給財源の準備
損害保険の種類と保険金額
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/08/i883.pdf
◆ネットジャーナル
日米欧の産業別の経済成長
消費者物価(全国25年7月)
~コア CPIは8月に 3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し
◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和7年6月実績および令和7年7~9月見通し)
◆経営情報レポート
変化に対応し採用力を強化する
中堅・中小企業における人材採用戦略
◆経営データベース
企業に求められる対応
ハラスメント対策との違い
◆トランプ関税の根源は米国財政の行き詰まり このままいけば破綻も
◆冥加とは「神仏や先祖の御加護」が加わる力
◆米国は、アジア依存に戻らず
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/08/1417.pdf
令和7年も気が付けば残り4か月。ふるさと納税を考えている方もいるのではないでしょうか。
そのふるさと納税をする際、ポータルサイトを通じて各地方団体に寄附を行った場合のポイント等の付与が、令和7年10月から禁止されることはご存じでしょうか。
ポータルサイトでのポイント等が付与されるのは9月末までとなります。
ふるさと納税制度では、適正な運用を確保する観点から、制度趣旨に反する一定の募集を行う地方団体を指定団体として認めないこととしています。
禁止される一定の募集方法には、「特定の者に対して謝金等の供与を行うなどの不当な方法による募集」などがあります。
令和6年6月28日の告示改正により、令和7年10月から、禁止対象に「寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益を提供する者を通じた募集」などが加わりました。
各地方団体がポータルサイトに委託料を支払って、返礼品等の情報を掲載してもらうこと自体は、禁止される募集方法のいずれにも該当しないのですが、寄附者がポータルサイトを通じて寄附を行い、ポータルサイトから寄附者に付与されるポイント等は、上記の「寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益」に該当するのです。
現行では、各ポータルサイトが定める還元率に応じて、寄附額の一定割合のポイントやマイル等が直接的に寄附者に還元される仕組みのほか、ポイントサイト等を経由してポータルサイトに遷移し寄附を行った際に寄附に伴って間接的にポイント等が付与される仕組みなどが存在します。
令和7年10月からは、直接、間接を問わず、いずれの仕組みも上記の「寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益」に該当するものとして禁止されてしまいます。
ふるさと納税を検討している方は、早めに寄付をされた方がよさそうですね。
また、ふるさと納税をした場合は確定申告が必要になります。ご不明な点がありましたら、税理士法人優和へお問い合わせください。
東京本部 渡辺
◆医療情報ヘッドライン
国立大学病院の赤字が過去最大に
「来年度赤字幅は増加」との予測も
特定機能病院の逆紹介割合が低水準に
24年10月の平均値が減算基準を下回る
◆週刊 医療情報
地域包括医療病棟の届け出、
180病院超え
◆経営TOPICS
最近の医療費の動向
概算医療費(令和6年度2月号)
◆経営情報レポート
介護保険制度の安定性・持続可能性を追求した
令和6年度 介護報酬改定の概要
◆経営データベース
診療部門における事故防止のポイント
医療廃棄物処理のリスクマネジメント
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/i880.pdf