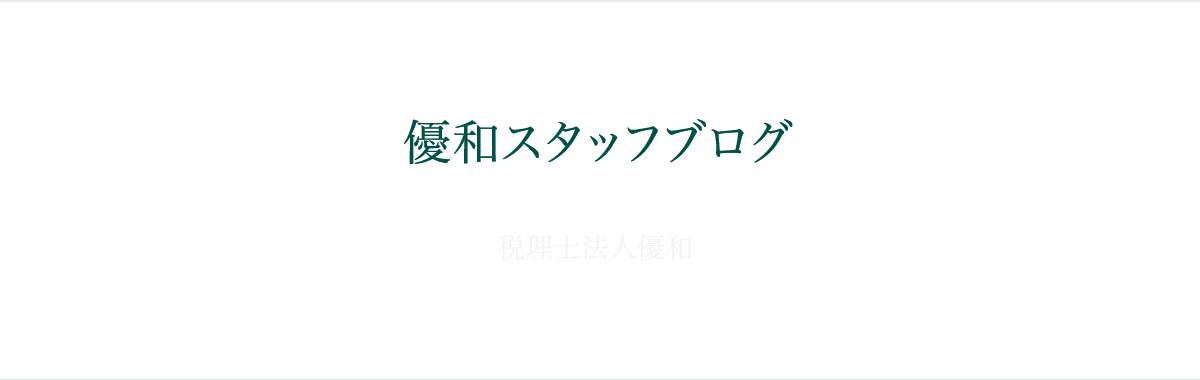
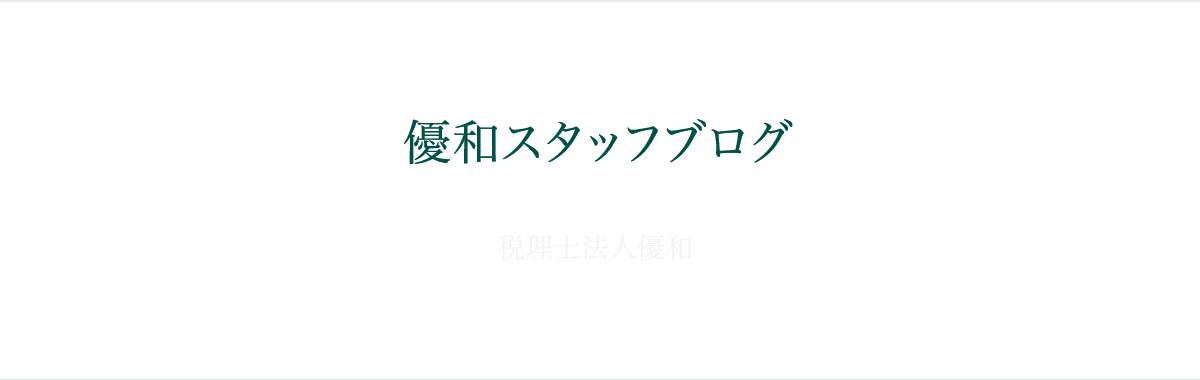
「もし親が認知症になったら」──多くのご家庭で心配されるテーマですが、実際にどんな影響が出るかを具体的に
理解している方は少ないかもしれません。
認知症になると、単に生活上のサポートが必要になるだけではありません。法律的な「判断能力」が失われることで、
財産管理や相続対策に大きな制約がかかります。
例えば、遺産分割協議への参加、不動産の売却、遺言書の作成、名義変更、贈与契約、生命保険の加入・解約といった
手続きは、いずれも「本人の意思確認」が求められます。
そのため、認知症を発症して判断能力が失われると、これらの行為がすべて“できなくなる”のです。
「認知症=法律行為の制限」という現実を踏まえずに対策を後回しにしてしまうと、資産の凍結や税務上の
不利益につながることがあるのです。
認知症対策として、代表的な2つの方法、「成年後見制度」と「家族信託」についてご説明します。
どちらも判断能力の低下に備える制度ですが、その目的と使い勝手には大きな違いがあります。
成年後見制度は、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産を法的に保護する仕組みです。
【メリット】
・法律に基づく強力な保護が受けられる
・後見人が不正を防ぎ、財産が守られる
【デメリット】
・家庭裁判所の監督下に置かれ、使途の自由度が低い
・本人の利益のため以外には財産を動かせない
・手続きや報告に時間と費用がかかる
つまり、「財産を守る」ことに重点が置かれた制度といえます。
一方、家族信託は、元気なうちに信頼できる家族(受託者)に財産を託し、将来の管理や処分を任せる仕組みです。
認知症になっても、受託者が契約に基づいて柔軟に財産を活用できる点が大きな特徴です。
【メリット】
・認知症後も資金移動や不動産売却がスムーズ
・家族の判断で柔軟な対応が可能
・遺言代わりとして相続承継の設計にも使える
【デメリット】
・設計を誤ると贈与税などの課税リスクがある
・信託契約書の作成に専門知識が必要
つまり、家族信託は「財産を活かす」ための制度といえます。
どちらが優れているというより、ご家庭の目的や状況によって使い分けが大切です。
認知症になると、遺言や贈与など生前対策や税制上の特例が活用できなくなるケースが多く、結果として相続税が
増えることもあります。元気なうちに「家族のための仕組み」を整えておくことが、将来の安心と節税の両方に
つながります。
京都本部 良川