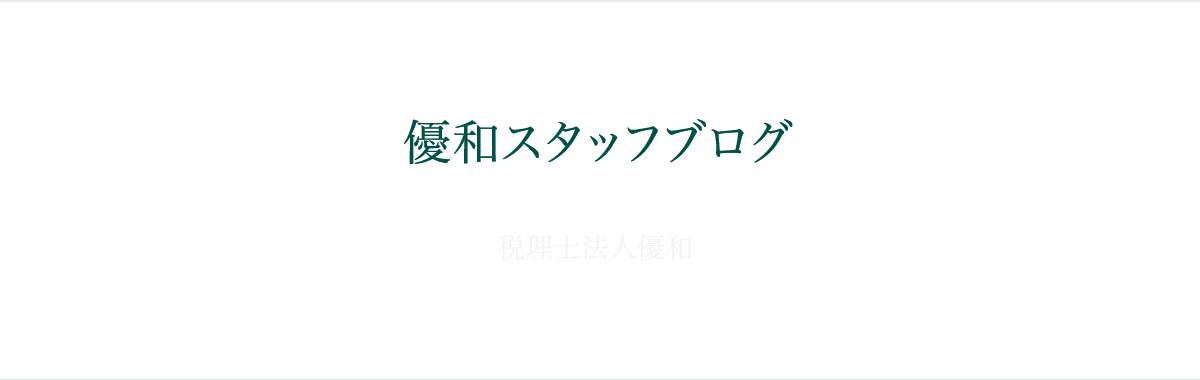
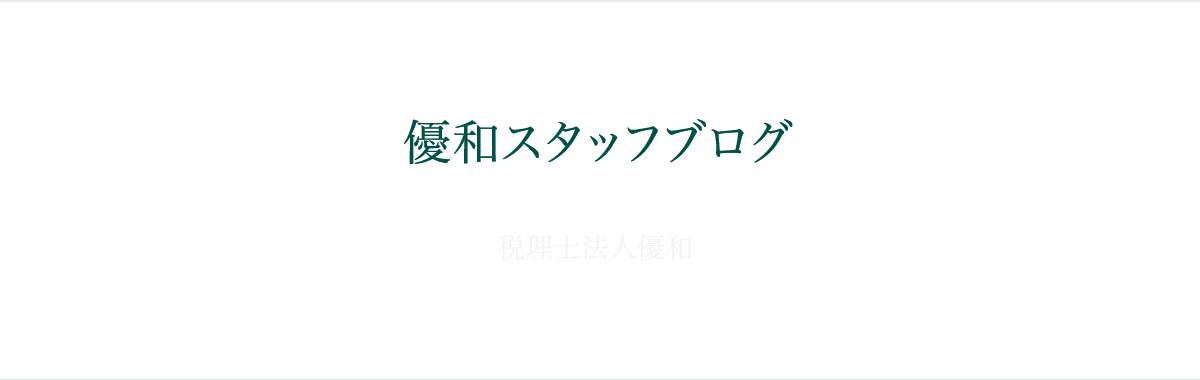
相続税の非課税項目の中で、生命保険金の非課税というものがあります。
受け取った生命保険金等の金額の合計額のうち「500万円×法定相続人の数」相当の金額までは非課税・・・というものです。
ただし、これは相続人のみ適用を受けることが出来る制度ですので、もし相続人の中で相続放棄をしている人がいたら、その方には適用されませんので注意が必要です。
被相続人A、妻A’、子Bのご家族で、子Bが相続放棄をしたとします。ここで、妻A’子Bがそれぞれ生命保険金を受け取った場合(相続放棄をしていても生命保険金の受取人であれば受け取ることができます。)に、妻A’には相続税の非課税が適用されますが、子Bは相続人の立場を放棄していますので、この非課税制度は適用されません。
相続税の計算には『相続税の基礎控除』というものもありますので、課税される金額があるかどうかは別の話ですが、制度の適用にはあらゆることを鑑みつつ慎重を期さなければいけません。
東京本部 酒井
自宅で元々猫を飼っていたのですが、先週よりもう1匹子猫を迎えることになりました。
先住猫は突然やってきた子猫にびっくり。
初めは子猫が近づいてきたら、先住猫は威嚇して猫パンチをしていました。
しかし日が経つごとに威嚇がなくなり、2匹でじゃれ合って遊ぶようになりました。
お互い毛づくろいをするようにもなり、1週間で2匹がこんなにも仲良くなれたことに感動しています。
人間と同じで猫同士も相性があるようで、2匹が仲良くなれるか心配でしたが一安心です。
京都本部 金原
春から今までの生活と全く変わってしまい、何事も細心の注意を払う日々となりました。
人との接触を減らすとのことで、ZOOMなど画面を通してオンラインの交流が増えたのではないかと思います。
私も自宅にて座学の講座や講演、ヨガやエアロビクス、体幹トレーニングなどオンラインで受講する機会が増えました。
本当ならその場に行って同じ空間を共有できるのがベストなのですが、オンラインでその場には行けなくても同じ時間を共有できるのは、移動時間の短縮と、周囲に気をつかわず集中してできるのでいいではないかと感じています。
毎回エアロビクスを受講しながら思うのは、カメラが映る範囲の限られたスペースで行うので動きがワンパターンになりがちですが、毎回ワンパターンにならないようレッスンを工夫して提供してくださるインストラクターさんの力量に脱帽です。
今後もリアルレッスンとオンラインレッスンをうまく併用していけたらと思います。
埼玉本部 鈴木
後期生になり、この夏、語研修のため、ニュージーランドホームステイに行く予定が中止、部活動もコンクール、イベントetc全てが中止となり、我が子だけの話ではありませんが、大人以上に子供たちはストレスのたまる?モチベーションを保つのが難しい日々を過ごしているように思います。
そんな中、今月末、体育祭は行われることになったようで、実行委員になっている娘が、お盆休み中もビデオ通話を利用して諸先輩方と意見交換している姿が新鮮でした。今日までが期末テストなのですが、朝からすでに体育祭の事で頭がいっぱい(苦笑)。今までのような活動は難しいですが、精一杯高校生活の思い出作りしてほしいと思いました。
体育祭では吹奏楽部としての演奏も、春に中止になってしまった文化祭の有志出し物もやるらしいのですが、密を防ぐために父兄の見学ができないことが残念です(涙)
早くワクチンが開発されることを祈りましょう。
茨城本部 香取
あまり有名ではないですが、国税には意見聴取という制度があります。
簡単に言うと、申告書に「書面添付」が付されている場合には、税務調査を行う際、事前に税理士に意見聴取を行うことが必要になるという制度です。
この「事前に」というのがポイントで、税理士に対する意見聴取の結果、調査がなくなる(調査省略)という結果もあったりします。(私の過去の実績では、4社中3社が調査省略になりました!)
書面添付の記載内容は、基本的には調査で指摘されるだろう事項を予め記載するというものになります。そのため、会社様我々ともにハードルは高くなりますが、調査という時間を省略できる唯一の制度ですので、ぜひご検討いただければと思います。
東京本部8階 木村
先日、久しぶり(記録によれば16年ぶり)に近くの献血ルームに行き献血をしてきました。コロナの影響により献血する人が少なく、血液が不足しているというニュースをやっていたからです。(特に私の血液型であるA型が不足しているということだったので。)献血をすると、血液の検査結果を郵送で送ってくれるということもやっています。先日、結果が届き、おかげさまで異常はありませんでした。 機会があれば、また献血に行きたいと思います。(前回の献血から3ヶ月開ける必要があります。) 皆さんも近くの献血ルームを探してぜひ行ってみてください。ジュース飲み放題 アイスクリームも食べれます。帰りに色々もらえます。
東京本部:佐藤
8月も残すところわずかとなりました。
お店では秋の味覚の新商品や、秋服がもう並び始めていますね。
気温的にはまだまだ夏が続きそうですので、熱中症に気を付けていきましょう。
京都本部 金原
藤井聡太が二冠を達成し、最年少記録を更新するなど最近の若い人の活躍は目覚ましいものがありますね。
そして個人的には今夜の全英女子オープン2日目も楽しみです。去年の渋野日向子選手の活躍が記憶に新しいところですが、今回も渋野選手はじめ日本人選手の活躍を大いに期待してしまいます。
ついつい夜更かしして生で見てしまうんですよね。
日本人選手頑張れ~!
埼玉本部 瀬島
新型コロナウィルスの感染拡大がなかなか収束に向かわず、中小企業のお客様にとっては厳しい経営環境が続いております。
何とか、一日でも早くワクチンが開発され、マスクを付けなくて済むような普通の日常に戻ってほしいですね。
COCOAを私もインストールしました。日本全国で1000万人以上が既にダウンロードしているようです。出来るだけ多くの方に利用していただくことが、感染拡大を食い止めるためには必要ですので、是非皆様もご利用をお願いいたします。
明けない夜はない、一緒に頑張っていきましょう。
茨城本部 楢原
8月に入って、やっと梅雨明けになり、厳しい猛暑日が続いてきました。
去年の今頃を振り返えて見ると、休みの日はいつも家族、友人との集まりが多くて、新しい観光地の訪問、子供達と面白い遊びの体験、友人からの懐かしい故郷お土産(ライチと龍眼)の味わいなど楽しいことがつぎからつぎへ待っているようでありました。しかし、今年に入ってからは、コロナの影響で、遠く離れている家族、友人とはテレビ電話でしか会えないことになり、会話ももちろんコロナの話ばかりでありました。
まだまだ感染者数が増え続けている一方、熱中症も油断できない今の時期、皆様ぜひ体健康に気をつけてください。
最後、20年間白血病と戦ってきて、今も闘病のなか、執筆と講演活動を通して大勢の人を応援し続けてきた親友からの一言葉を共有したいと思います。原語(韓国語)を直訳すると、「幸せだから笑うのではなく、笑うから幸せなのだ」です。
今日も皆様にとって良い一日になるよう、お祈りいたします。
東京本部 呉