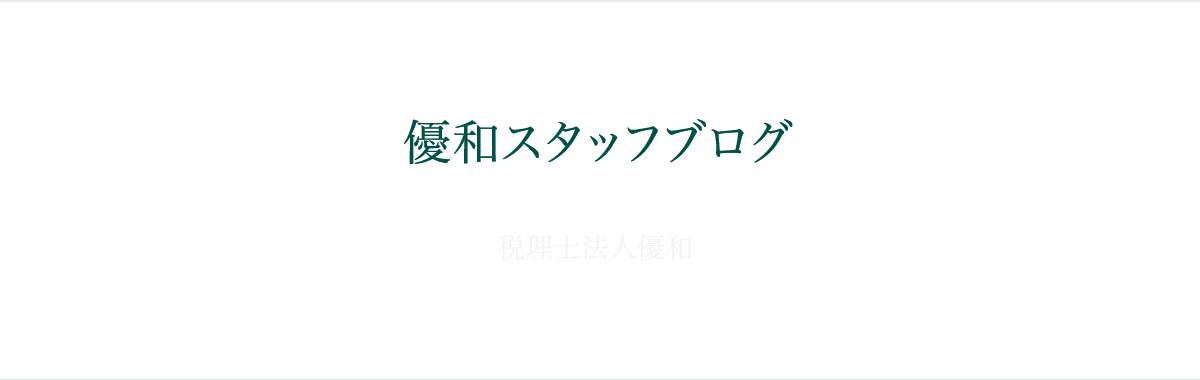
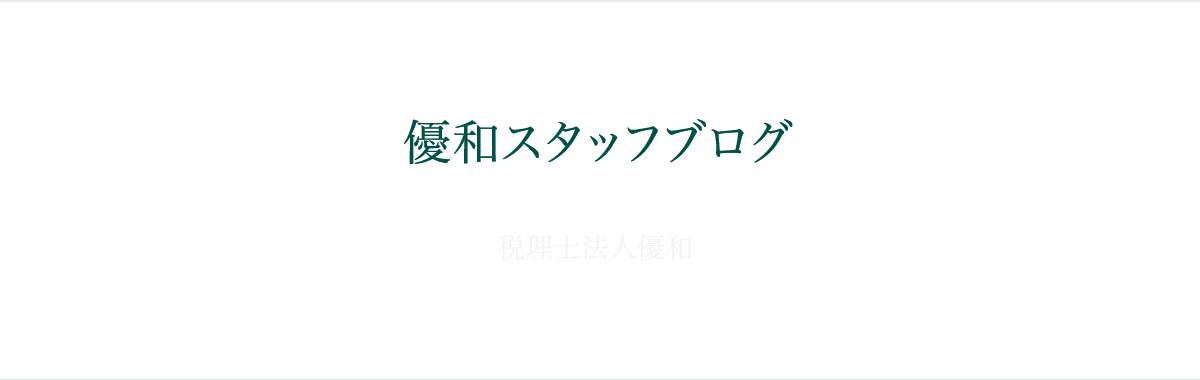
暑かった10月前半とは打って変わって一気に寒くなってきました。
寒暖差が激しくなると体調を崩しやすくなりますので、健康面には十分気を配っておきたいものです。
さて、今年も残り2ヶ月となり、会社に勤めている方は年末調整の準備に取り掛かる時期となりました。
自宅に各種保険料の控除証明が届いているかと思いますので、会社へ提出することになります。
一方で、保険料以外でも税負担を抑えられるものもありますので、一部ですが列挙していきます。
1.勤労学生控除
通常、年間103万円を超えると所得税がかかってきますが、
給与を得ている学生で年間130万円以下であれば、所得税はかかりません。
対象となる学生は高校や大学の他、専修学校や職業訓練校などで一定の過程を履修している場合が対象となります。
ただし、勤労学生控除が適用できても親の扶養から外れることにはなります。
2.寡婦控除
後述するひとり親控除に該当しない方で、次のいずれかの条件に該当する場合に適用されます。
ただし、男性については対象外となります。
①夫と離婚した後再婚せず、扶養家族がいる人で合計所得金額が500万円以下の人
②夫と死別した後再婚していない、または生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。
この場合、扶養家族の要件はありません。
3.ひとり親控除
結婚していない又は配偶者の生死の明らかでない場合で、次の3つの要件を全て満たす場合に適用されます。
こちらについては男性も対象となります。
①その人と事実婚と同様の事情にある人がいないこと
②扶養する子供がいること、この場合、子どもの総所得額が
48万円以下で他の人の扶養家族となっていないことが条件となります。
③合計所得金額が500万円以下であること
寡婦控除よりも条件は厳しいですが、対象になれば所得税額を抑えることができます。
4.障碍者控除
心身に何らかの障害を持っていて、役所より手帳の交付を受けている又は認定を受けている場合に適用される制度です。
これは本人だけではなく、配偶者や扶養家族にいる場合も対象になります。
以上となります。
自身が条件に合致するか分からない場合もあるかと思いますので、税理士法人優和までお気軽にお問合せください。
京都本部 橋本(直)
2021年分の確定申告からふるさと納税の申告手続きが簡素化されます。現行では、ふるさと納税で寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされておりますが、この寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することで済むようになります。
寄附金控除に関する証明書を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者で、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされております。昨年末現在で登録されている特定事業者は、「ふるなび」、「さとふる」、「楽天ふるさと納税」、「ふるさとチョイス」ですが、今後登録数は増えていくとみられております。
今年のふるさと納税から寄附者は、これらの特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を申告書に添付するだけで済むので、申告手続きが大幅に簡素化されます。同証明書には、(1)寄附者の氏名、住所、(2)その年中の寄附者の寄附総額、(3)特定事業者が寄附を管理している番号、(4)寄附年月日、(5)寄附先の名称及び法人番号、(6)その他参考となるべき事項、が記載されます。
確定申告の際には、(1)特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信、(2)特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告、(3)郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告、のいずれかの方法により行うことになります。
なお、(2)のQRコード付証明書等作成システムについては、2021年 10月頃に更新し、「寄附金控除に関する証明書」の出力に対応する予定となっています。また、確定申告が不要な給与所得者等が利用できる「ワンストップ特例制度」には変更はなし。ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。
埼玉本部 秋元
先日、SNSでこのような内容の投稿を目にしました。
『山手線のホームに並んでいる人たちがいて、駅員さんがずっと「このホームに並んでいても山手線は来ません!今日明日は終日来ません!」(渋谷駅の改修工事のため、終日一部の区間で運行中止)てメガホンで叫んでいるのにぼんやりみんな並び続けてた 気が狂うかと思った 』
自分がその場にいたわけではないので詳しい状況はわかりませんが、この投稿を読んで興味が沸いたのが、ずっと前から各メディアや駅内ポスター、放送等でこの日は山手線は一部区間は運休ですというお知らせはされていたのにも関わらず、知らずに並んでいる人たちがいて、状況が理解出来ていないのか、みんなが並んでるから自分も並んでいようと周りに便乗する日本人の感覚。自分たちに向けられた内容であると処理できないのか、周りが動かないから正常性バイアスで動かないのか…。または違う理由があったのでしょうか。
今回の事例に限らず、このような現象って少なからず日常のどこかにありますよね。
自分に向けられた言葉は、ちゃんと聞く耳を持つことを常に心掛けたいと感じるニュースでした。
茨城本部 青木
『10月はたそがれの国』と言う題名の本があったが。
季節の変わり目、特に秋が深まり行く頃などは。空気も、空も、風も、そして漂う光や匂いも。どこか、どっちつかずと言うか戸惑いが感じられて。その輪郭の曖昧さが優しく感じられもする。そんなものを愛しく思えるのは、そんな表現が数少なくあるのは、白黒をハッキリさせるだけが総てではないと教えてくれている気もする。
しかし。そんな季節の終わりに訪れる意思表明の機会、権利。そこにはある程度、ハッキリとした思いで臨まねばならないのだと。そう心する、たそがれの季節の日々である。
東京本部 本多
暑かった夏も過ぎ、朝夕が過ごしやすくなってきました。
緊急事態宣言も解除され、町にも徐々に人が戻ってきたように感じます。
京都本部のある京都府では、「宿泊施設事業継続緊急支援事業補助金」の2次募集が開始されました。
新型コロナウィルス感染症の影響により、大きな打撃を受けている京都府内の宿泊事業者を支援するため、
宿泊施設における感染防止対策の取組や、新しい生活様式に対応した事業展開に対する補助をすることを趣旨としています。
詳細については下記リンクをご参照ください。
宿泊施設事業継続緊急支援事業補助金について(2次募集)|新着情報|京都“府”観光ガイド ~京都府観光連盟公式サイト~ (kyoto-kankou.or.jp)
この他にも国、地方公共団体による補助金等がありますので、ぜひご活用ください。
京都本部 橋本
岸田総理が10月14日衆議院を解散して10月31日投開票の総選挙となることが正式に決定した。13日に移動中の車内から選挙ポスター用の掲示板が既に設置されている光景が目に入り、多少の違和感を覚えたが・・・。
さて、日本の選挙と言えば候補者が選挙カーで選挙区を廻り政策を訴えるのがおなじみの光景だが、先日お昼に見たテレビで紹介されていたノルウェーのそれは、日本のものとはかなり趣を異にするものであった。選挙期間中ロードサイドに選挙小屋が建ち、そこでは議員や党員が市民からの質問に答えたりしながら政策を訴えていた。
子供であっても積極的に選挙小屋に赴き質問を投げかける。なぜか?実は訪れた子供たちには政党のグッズやお菓子・ジュースなどが配られるため、また宿題として選挙小屋の訪問が出されたりするため、期間中に選挙小屋は子供たちの姿も多く見かけるそうだ。
そのおかげか否かは定かではないがノルウェーでの若者の投票率は日本よりもはるかに高いらしい。ノルウェーの若者からしたら選挙カーに乗って候補者の名前を連呼するだけの選挙風景って違和感しかないでしょうね?
埼玉本部 KY
先日、コロナワクチンの2回目の接種を終えました。
当日は接種部位の痛みくらいしか目立った症状がなかったので、この程度なら翌日に影響が出ないなと思い眠りについたのですが、夜中に関節痛とも筋肉痛ともいえるような痛みで目が覚めました。接種部位を中心に首や背中に痛みが走り、熱を測ってみると38度を超えており、結局、市販薬でごまかしながら症状が治まるまで2日ほどかかってしまいました。
世間では3回目が必要だという声もあがっていますが、またこれを味わうと思うと気が重くなります。
これを読んでいる方の中で2回目の接種を控えている方がいらっしゃいましたら、大分症状が緩和されますので解熱鎮痛剤を準備しておくことを強くお勧めします。
茨城本部 大島
今年の6月に入社した伊藤です。簡単に自己紹介をさせていただこうかと思います。以前はクリニックで医療職をしていました。患者さんに穿刺をしたり機器のメンテナンス等をしていました。毎日立ちっぱなしで足の裏がまっ平になるんじゃないかと思ってましたが今は座りっぱなしでお尻がまっ平になるんじゃないかと思ってます。医療職として働いていたときから会計に興味がありました。先輩方に教えて頂きながら勉強し少しでも早くお仕事に慣れていきたいと思います。
皆様、コロナワクチンの接種は終えられたでしょうか?
私は今月半ばに接種する予定です。
接種を終えた職員の様子を見ていると、
高熱を出した方もいれば、なんともなかった方もいます。
9年前にインフルエンザに罹った時を最後に熱を出していないのでドキドキしています。
熱が出たときのために万全の体制を整えて接種に臨みたいと思います。
京都本部 金原
当事務所の道路を挟んで向かい側にあるお店をご紹介します!
お店の名前は縄文庵さん。
週に一度お邪魔しておりますが、毎度毎度お野菜タップリでめちゃめちゃ手をかけたお料理を提供して下さいます。
お夕飯用にお惣菜もお願いしてテイクアウトしています。
是非是非行ってみて下さい!


上がメインのおかずで、下が初めに出てくる前菜?のようなもの。
これにご飯とお味噌汁(お味噌も手作りです)がついて税込1,100円
追伸 お冷もハーブ水で毎回3杯は飲んできます(笑)
埼玉本部 斉藤