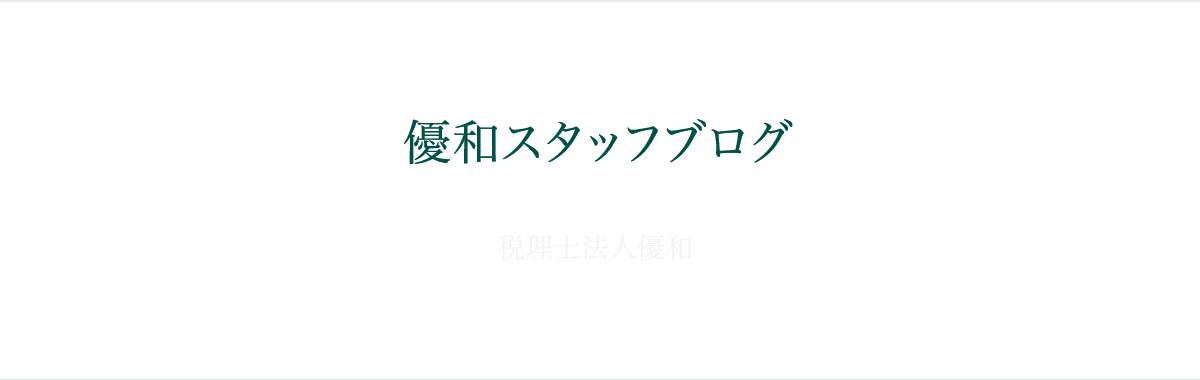
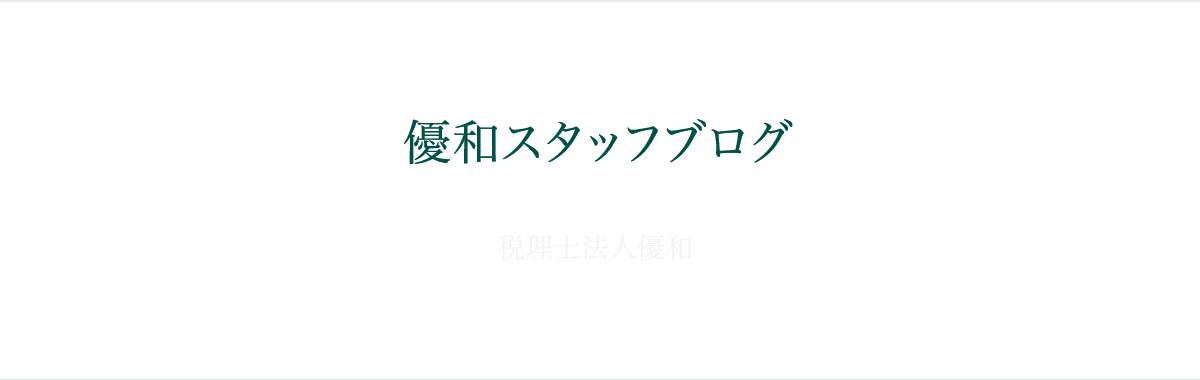
『凛として・・・』今までに幾度となく、耳にしてきた言葉。しかし、私は先日、久しぶりに、頭にさえぎり、しばらくの間、自分自身で、考える時間を持った。 と言うのも、先日、『一澤信三郎帆布物語』著者 菅聖子氏の本を読んだからである。通勤時間を利用して、いつも本を読んでいるのであるが、気がつくと、緊張しながら(背筋を伸ばし)又、ワクワクしながら読んでいたのです。本の箇所においては、不適切な言葉となるかもしれない。が、奥様の言葉、立ち振る舞い等、まるで、私の目の前での出来事のように、映像として流れていたからである。その時、頭の中は、この方のような人を凛として・・・って言うんだとずっと思いながら、読んでいたからです。毅然と、優しく、周りに接し、女の一生岩をも通すと言う言葉がぴったりでした。目指す女性像は又一人増え、感動した本でした。 京都本部 下田
「社会保険庁から何やら書類が届いているから見てくれない?」
今年で69歳になられた担当先の社長のところを訪ねてみると、届いていたのは「ねんきん定期便」だった。これまでの年金加入記録の確認のために、社会保険庁が定期的に送付してくれる書類だ。開けてみると、そこにはこれまでの年金加入記録が標準報酬月額と保険料納付額という形で月別に記載されている。記録は昭和39年、社長がまだ23歳の若いお嬢様だった時から始まり、A4サイズの用紙4枚にわたって全く途切れることなく記されている。
「よくここまで調べたわよねぇ」
社長は感心したような呆れたような口調でおっしゃるけれど、僕は迂闊にも感動してしまっていてすぐに返答ができないでいた。
「こんなの合ってるか違ってるかって言われてもねぇ」
それは僕も同感だ。確かにそこまで古い資料がある筈もなく、せいぜい直近数年間分の賃金台帳を確認する程度しかできない。
でも「ねんきん定期便」の本来の目的とは違ったところで話が弾んでいった。亡くなられた先代の社長のところにお嫁に来てからしばらくは無給で働いたこと、しばらくして当時の大卒初任給並みのお給料をもらい始めたこと、お店がどんどん儲かって従業員をたくさん雇っていた頃のこと、たくさんの思い出話に花が咲いた。
先代の社長が亡くなったのを機に長く地元で愛されたお店をたたみ、今は建物を賃貸して社長が一人で会社を守っておられる。
人が働くところには様々なドラマがある。そんなドラマをごく近しいところでサポートできるこの仕事には責任が伴うと同時に大きな魅力があると思う。何年やっても進歩しない自分に時々嫌気がさしたりもするけれど、前向きに成長していければいいかと思う今日この頃でした。
松山本部 坂野
子供の絵が全国染織連合会主催の「きものデザインコンクール」で
3年連続入選させていただきました。
今年もデザイン画を描いたと聞いてはいたのですが、入選の知らせ
をいただいた時はびっくりしました。
1年目は着物に、2年目は帯にしていただきました。
3年目は・・・残念ながら作品にはなりませんでした。
二条城二の丸御殿に展示されているとのとでしたので、親バカなが
ら見に行ってきました。
ちなみに、二条城は徳川将軍家康が、京都御所の守護と将軍上洛の
ときの宿泊所として造営し、3代将軍家光により伏見城の遺構を移
すなどして1626年に完成したものだそうです。
京都N
先日友人たちが、お祭りで催されるおばけ屋敷のおばけになる、ということで誘われて出かけました。
おばけ屋敷に入るのを楽しみにしていたのですが、なんと急遽私もおばけ役として参加することになりました。
私の役は「小豆洗い(あずきあらい)」という妖怪。
おばけたちは名演技(?)でお客さんを次々と怖がらせていました。
お客さんは大抵が子供、または親子連れでした。
子供たちは泣き出したり、「怖くない!」と強がったり、入り口から少し行ったところでもうUターンする子もいました。
大人の男性が1人で入って来られているときがあり、
「どうやったら怖がってもらえるのだろう…」と
その人が近づいてくる間、必死に考えていたのですが、
私がタイミングよく立ち上がっただけで非常に怖がっていらっしゃいました。
怖がりだったのですね…
いけないと思いながらもそのものすごい怖がりようにちょっとだけ笑ってしまいました。
なかなかできない経験ができた楽しい1日でした。
松山本部 渡辺
京都の夏は、真っ盛りである。京都の三大祭の一つ祇園祭の真っ只中。
祇園祭は毎年7月1日に始まり、1ケ月間のお祭です。全国から、又、世界各地から宵山、山鉾巡行を見学にたくさんの方が京都にお見えになり、鉾には、外国人の方も参加されたりしています。京都本部の前を、巡行されますので、毎年、私たちは、見せて頂く有難い場所で、仕事をさせて頂いているのです。お客様には、巡行に参加されている方もおられ、7月は仕事より、巡行の事が大事と言い切られております。
山鉾巡行が終わると、花笠巡行、狂言奉納、御輿洗いなど、31日に向かい、行事があり、又、山鉾巡行とは違う、祇園祭が見る事が出来るのです。
鱧もおいしいこの時期、再度、お越しになりませんか?
京都本部 下田
少し前の話になりますが、ある雑誌に歯科医のワーキングプアに関する記事が載っていました。日本の歯科医の5人に1人は年収300万円以下というものですが、最初この話を聞いたとき、いまひとつピンときませんでした。皆さんも同じだと思うのですが、一般的にはお医者さん、歯医者さんは裕福というイメージがあります。人と話をしていても「知っている歯医者さんは皆外車乗ってるけどなあ、ほんまかいな。」というような意見が大勢を占めます。しかし先日ある歯医者さんと話をしていて状況はかなり深刻ということがわかりました。
日本は戦後しばらく衛生面であまり行き届いていない時期があり、そこに急激な経済発展により飽食の時代になったため世の中に甘い菓子類などが氾濫し、その結果、町の歯医者さんには虫歯になった子供が溢れかえる事態になったとのことです。
これではいけないということで日本全国で歯科大学が新設され、歯医者さんが急増しました。しかしながら皮肉なことに、逆にその頃から虫歯予防の良い歯磨き粉が出るようになり、小学校などで歯の磨き方の指導が徹底されるようになったため歯医者に来る子供が激減し、慢性的に歯医者さんが過剰な状態になったとのことです。加えて歯医者さんは一人前になるためにはどこかの現場で研修医として修業を積む必要があります。お医者さんであれば内科、外科その他細かく専門分野が分かれていて、大学病院でもかなりの勤務医を必要としているため就職には困らないのですが歯科の場合は町の歯医者さんで働くぐらいしかありません。しかし雇う側でも患者が少ない中で高給を払うこともできず、中には経験を積むために無給でも構わないという人もいるそうです。これは完全に構造的なものであり、ここにきて国家試験を難しくして、さらに狭き門にし、歯医者さんの絶対数を減らす方向になってきているとはいえ、この状態を脱するには最低10年はかかるとのことでした。もちろん歯医者さんの中にもしっかり収入を得ている方も多くいらっしゃいますが、そういう方たちは患者を呼び込むため、いろいろアイデアを考えたり、プラスアルファの努力をされています。
最近、不況の影響で資格を目指す人の数が急激に増えているとのことですが資格を取っただけでは食べていけない時代であり、その後の努力が大事ということでしょうか。
京都本部 古吉
父の日に小学校の休日参観がありました。
子供は小学6年生です。
1時間目は算数、2,3時間目は「かがやき」という
選択制の体験授業でした。
子供は「茶道」を選択しており、茶道室でお菓子と
抹茶をボランティアのお茶の先生から習った作法で
もてなしてくれました。
子供の通う学校は小中一環教育として、小学6年生から
中学3年生までが同じ校舎で学んでいます。
また小学生は「御所南小学校」と「高倉小学校」の2校
の生徒が通っています。御所南小学校の6年1組は
「6G-1」という教室があり、高倉小学校の6年1組は
「6T-1」の教室があります。中学1年生は7年生、2年生
は8年生、3年生は9年生と教室が表示されており、
建物が7階建てということもあって、目的の教室を探し当てた
ころには息切れしていました。
体験学習などは伝統産業だけでなく、多くの一般企業経営者の
ボランティアに助けていただいています。
優しく、素敵な方々に子供を育てていただいているということに
あらためて感謝の一日でした。
これは毎年思う事なのですが、梅雨入りしてからすぐはそれらしい天気を実感する日が少ない気がします。
でも今週は雨が多くなるようです。
予報通りなら本格的な梅雨の季節となりそうですね。
わたしは毎日のように雨が降って欲しいくらいです。
別に梅雨が好きなわけではなく、先週から家の庭の水遣りを頼まれているからです。
家の周りをぐるりと撒く必要があるのですが、これがちょっと面倒なのです。
長いホースでだいたいカバーできるのですが、玄関へはどうもホースの長さが足りない。
さらにホースの長さが仇となって、あっちへこっちへと引きずっていると引っかかってしまいます。
玄関へは仕方ないのでじょうろを使って2回ほど往復。
これを毎日する必要があるのです。
でも雨さえ降れば不要になります。
この水遣りの任務は今週一杯です。
毎日雨が降ればいいのに。
出来れば1~2時間降ってすぐ止んでくれたら文句ナシなのですが、そうもいきませんよね。
京都本部 村上
もうすぐGWです。計画を立てながら、楽しみにされている方も多いと思います。
私のGWは実家に帰って、父親の還暦祝いを家族で行う予定にしています。
気がつけば、父親もそんな年齢になったかと思いながら、プレゼント選びを楽しんでいました。
振り返ると、父親は毎日働きっぱなしの人生だった様に感じます。
父親の唯一の趣味が温泉に行くことなので、還暦祝いも温泉に行って食事をする予定です。
まるで私一人で計画した様に書きましたが、発案から予約まで母親と嫁が率先してやってくれました。父親へは勿論のこと、家族のみんなに感謝です。
今年の秋には弟の結婚が控えているので、そのときは私が率先して計画したいと思います。
京都本部 大林 勲生