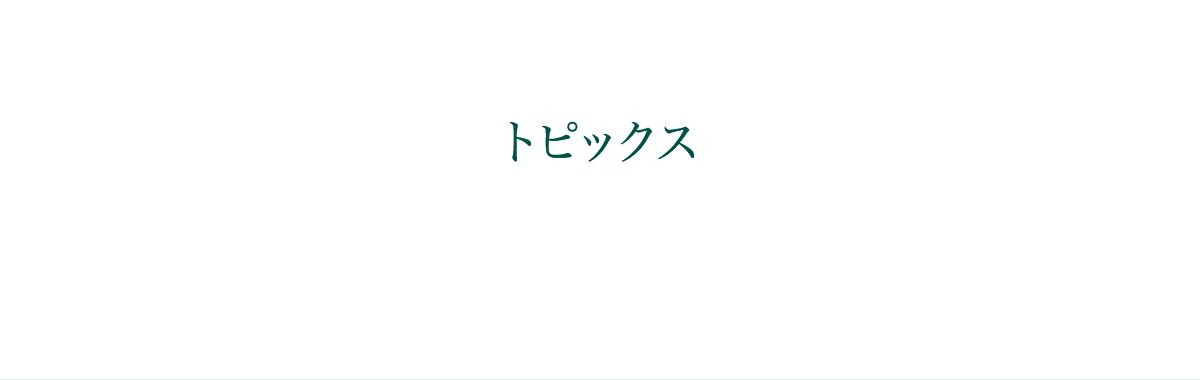
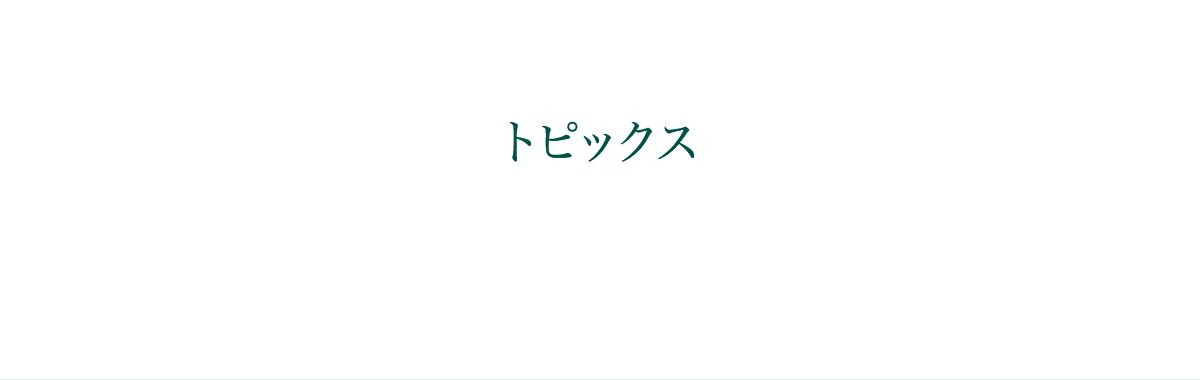
最近になってコロナ感染者が急激に増加していることもあり、以前のようにテレワーク・時差出勤の推進等に伴い、通常業務に遅延が生じている会社も多いことかと思います。
御存知の通り役員報酬については通常株主総会の決議を経て決定されるものですが、その株主総会の招集・決議を実行することすら難しい状況が続いていくことが今後予想されます。そこで、株主総会が大幅に延期した場合の役員給与の損金算入について、また、事前確定届出給与についてご案内したいと思います。
役員報酬のうち損金算入ができるものの一つとして挙げられている定期同額給与は、その要件のひとつに、「通常改定」によるものは、会計期間開始の日から3月を経過する日までにその改定を行うこととされています。
これに加えて、3月経過日等後になってしまった場合には「特別の事情があると認められる場合」には、その改定は認められるとされています。
今回のように大幅に株主総会の開催が遅れた場合などの取り扱いについては、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」において、情報として公表されています。
そのFAQによれば、「このような状況(=新型コロナウイルス感染症の影響による定時株主総会の開催時期の延期)により、定時株主総会に合わせて継続して毎年所定の時期にされる役員給与の通常改定が3月経過日等後に行われる場合には、自己の都合によらない「特別の事業があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定の時期の要件を満たすことになります。」と説明されています。
次に事前確定届出給与については、「提出期限」は、原則として、株主総会等の決議により事前確定給与の定めをした場合における当該決議の日から1月を経過する日とされ、同日が当該開始日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には、当該4月経過日等とされています。
今回のように株主総会の開催時期が遅れる場合については、経済産業省からのペーパーにはなりますが、「新型コロナウイルスの影響により株主総会の延期等を行う場合の役員給与の損金算入について」において公表されています。そのペーパーによれば、今回のケースは国税通則法第11条の個別延長と対象となるので、届け出期限の延長が認められますと案内されています。
コロナウイルスの影響により、通常とは違う事案が発生することが多くなるとは思いますが、税務上確認したいことがあれば、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。
東京本部 木村
7月14日より家賃支援給付金の申請が始まりました。
こちらは半年間の家賃の補助がされ、法人は最大600万円、個人は最大300万円の給付がされます。
要件は今年の5月から12月の売上高の前年同月比が1ヶ月で50%以上減少している、または、連続する3か月の合計で前年同期比が30%以上減少している中小企業者等で土地・建物の賃料の支払いをしている方が対象となります。
こういった給付金を受けた場合の取り扱いについては、法人の場合は収入として税金計算に含まれます。
同様に個人も収入に含まれますが、持続化給付金の支給対象が主たる収入が雑所得または給与所得で確定申告した個人事業者等を含むことになりました。
通常、個人の事業所得で確定申告をしている方について持続化給付金は事業の付随収入として事業所得に含まれます。
一方で雑所得として申請した方については雑所得として申告し、給与所得で申告した方については一時所得として入金のあった年の所得として確定申告する必要があります。
これによって事業所得の方は諸経費や青色申告特別控除を控除することができます。
雑所得の方は経費のみの控除となり、一時所得の方は(「一時所得の対象となる総収入額」-「収入を得るために支出した金額」-50万円)×1/2という計算をすることになります。
そうして算出した所得から各種控除をして課税所得が出た場合は税金が発生するので計算方法がかわるということに注意してください。
その他には雇用調整助成金も同様に収入となります。
一方で非課税となる給付金等については以下のようなものがあります。
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金,給付金
・特別定額給付金 (一人10万円給付金)
・子育て世帯への臨時特別給付金
・学生支援緊急給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
給付金等よって課税関係が異なりますので申告漏れや非課税のものを申告してしまう等によって余計に税金を支払わないように気を付ける必要があります。
その他給付金の要件等を知りたい方等は是非一度税理士法人優和までご連絡ください。
京都本部 近藤
世界中がコロナショックに見舞われる中、気づけば6月、2020年も折り返しとなりました。今年は東京五輪開催を始め、春夏通しての甲子園大会等様々なイベントの中止も決定し、私含め、待ち望んでいた多くの方にとって2020年は間違いなく印象の深い1年になることでしょう。
経済の面においてもコロナウイルスは世界中に大きな打撃を与え、経済活動停滞への救済措置として世界全体で金融緩和・財政出動などの経済対策が行われました。結果として8.5兆ドル(900兆円)のお金が市場に増えました。これは世界のGDPの9.8%に値する額だそうで、コロナ前の世界に日本+ドイツの大国が2つできる程の経済的インパクトになります。
これにより、コロナバブルなんて言葉が生れるほど余剰資金が金融市場に流れ込んでいるということです。この「コロナバブル」により、一時コロナで暴落した株価が大きく反発する中、実体経済はというと・・消費が完全にコロナ前に戻るのはまだまだ先かという印象です(第二波が来ていますし)。現在の株価上昇を牽引しているのは金余りで恩恵を受けた個人投資家(一部のお金持ち)のIT関連株を中心としての「買い」だそうで、このことは2000年頃に起きたITバブル時のような状況が先行き起きる可能性を示唆しているとも言われています。(実際のバブルを私は知りませんが)
今がバブルかどうかは後になってみないとわかりませんが、コロナの影響を受けて各分野でIT標準化への推進は急務になっています。少しでも早くコロナが終息し、実体経済が株価に追いつく未来を願ってやみません。
茨城本部 青木
新型コロナウィルスの影響で、前年の同月比で50%以上売上高が減少すると持続化給付金の対象になる可能性があります。
そこで、一番多い相談は「当月の売上高はどうやって計算するの?」や「昨年度の○○月の売上高はいくら?」「うちはもらえる?」です。
結論から言うと、提出書類である「法人事業概況説明書」の該当月の売上高の50%以下になっていれば対象となる可能性があります。
そして、この売上高とは原則として実現主義で計算します。
簡単に言えば物を引渡した日あるいはサービスを提供した日に売上高を計上します。
なので、4月30日に物を引渡し、5月2日に入金された場合、売上高は4月分で計上します。5月売上ではありません。
しかし、去年の法人事業概況説明書の期中の各月を入金ベースで売上高を計算し、決算月で実現主義に訂正している場合はどうなるのでしょうか?
比較のために当月も入金ベースで売上高を計算しても良いのでしょうか?
この点経済産業省では触れていません。
触れていないということは制度の原則通り実現主義を適用すると思いますが、
去年の法人事業概況説明書の売上高が入金ベースで計上していれば前年の同月と比較するために、当月も入金ベースで売上高を計算しても良いという意見も多くあります。
けれども、この入金ベースだと意図的な不正が可能になってしまいます。
給付金を得るために、「月末の入金を翌月に回してしまえ」など・・・
そして、仮にこれが給付金目的であるか否か、故意であるか否かに関わらず、
不正を疑われれば、事後的に返還を求められる恐れもゼロではないと思います。
そう考えると、実現主義で比較した方が良い気がします。
去年の該当月の請求書と今年の請求書を比較して50%以上減少していて、かつ法人事業概況説明書の売上高との比較も50%以下になっている月を確認して申請すればほぼ大丈夫でしょう。
そして何より重要なのは、給付金申請で使用した売上台帳の売上高と今年の法人事業概況説明書の売上高の金額を合わせるということです。
特に会計事務所に申告書の作成を依頼している方はこの点の意思疎通が必要になります。
最後に、持続化給付金はスピーディーに申請者に届くようにするために事前の調査よりも事後的なチェックの方が厳しいとも考えられます。
なので、受給して満足するだけではなく、仮に調査されても耐えられるだけの準備は必要だと思います。
茨城本部 大河原
ここ最近、国・地方公共団体などから「もらえるお金」についてインターネットで検索することが本当に多くなりました。
その都度感じるのが、日本というのは徹底して縦割り行政だなぁと。この助成金は○○省のホームページ、この給付金は△△省のホームページ、この補助金は◇◇◇庁のホームページ・・・とわざと分かりにくくしているのでは?と思わずにいられませんでした。
税理士法人優和の2020.4.15トピックスにもありますが、このような「まとめた記事」がないと全てを把握するのにかなりの時間を要することになりそうです。
一部の助成金は、要件や申請方法が何度も変更(緩和なのでまだいいのですが)され、混乱される方もかなり多いと思います。そしてやっと申請が終わっても実際にお金がもらえるのに案外時間がかかったりします。
助成金・給付金・補助金は、その原資のほとんどが税金であることを鑑みれば国民がもらえる…というより国民のもとに戻ってくるという考え方もできるのではないかと思います。もっと手続きが速やかに進み、またその支給がもっと早くなって、一人でも多くの国民が「助かった」と感じられるようになればいいなと思います。
東京本部 酒井
新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策である10万円給付に関連して、マイナンバーカードを申請する人が増えているそうです。
10万円給付の申請には郵送申請方式とオンライン申請方式がありますが、オンライン申請方式はマイナンバーカードを持っていなければ利用できません。
マイナンバーカードといえば、令和元年分の確定申告書等作成コーナーでは令和2年1月31日よりスマートフォンやMicrosoft Edgeからマイナンバーカードを利用したe-Tax送信のサービスを開始。
また、9月にはマイナンバーカードを使ったポイント還元事業が始まり、キャッシュレスでチャージまたはお買い物をするとマイナポイント25%(上限5,000円分)が付与されます(付与期間は2020年9月~2021年3月まで)。
さらに2021年3月からはマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。
普及率が低いと言われているマイナンバーカードですが、少しずつ出来ることが増え、あると便利な世の中になっていくかもしれません。
新型コロナウイルスの影響に関するご相談などお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に税理士法人優和までお問い合わせください。
京都本部 玉生
私たちの税理士業界では、お客様から「会計士さん」だとか「計理士さん」といった呼ばれ方をすることがたまにあります。厳密に言うと異なるものですが、あえてその間違いを訂正するのも面倒だし、仮に「会計士さん」と呼ばれたところで何ら影響ないので私はいつもそのままスルーしてしまいます。
税務会計の仕事に携わっていると、同じように微妙にニュアンスが違う言葉でも何となく会話としては成り立つが、こちらに関してはスルーすることなく、しっかりその違いを認識していないと有らぬ誤解を招くこともあります。
例えば「数次相続」(すうじそうぞく)という文言があります。簡単に言うとある人がお亡くなりになったが、遺産分割が終わらないうちに遺産分割協議者の一人が亡くなってしまい、その相続手続きも進めなければならない状況を言います。
それと似た言葉で「相次相続」(そうじそうぞく)という文言があります。これは相続税法上の文言で、読み方としては、たった一文字の違いなのですが、最初の相続の相続人が最初の相続発生から10年以内に亡くなった場合の相続税の税額計算に関するものであり、数次相続のそれとは全く意味の異なるものです。
それでは、「再転相続」(さいてんそうぞく)についてはどうでしょうか。これは「数次相続」と非常に似通った文言ですが、ひとつ決定的な違いは発生した相続に関する承認もしくは放棄の意思表示の有無です。
「再転相続」は、相続するか放棄するかのジャッジをする前に次の相続が発生してしまったケースをいい、「数次相続」は、そのジャッジを示した後に次の相続が発生した場合のことです。
本来数次相続であるべきところを再転相続と言ったところで何ら影響のないことのほうが多いかも知れませんが、相続放棄の有無だとか相続人の確定だとかの実態を正確に把握できていないと遺産分割及び相続税額の想定といった初期始動にあたって思わぬ躓きもあり得ますので、本当はどちらの意味で言っているのかの意思疎通を間違えないようにする必要がありそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣
最近はコロナウィルスがより一層蔓延していて、益々緊迫感をましている状況にあります。顧問先様においても非常に不安定な経営を強いられているケースが多数あり、いち早く平常の世の中に戻ってもらいたいと思っております。
さて、心の落ち着かないなかではありますが、敢えて、職場の近況及び職場で嬉しかったことを書きたいと思います。
職場では、毎週月曜日と木曜日に朝礼を行い、職場の教養を読みつつ、職員持ち回りで近況や税務に関して最新情報の共有などを行っています。
賛否両論あると思いますが、社内では大規模な会議は行わず、必要に応じて特定の社員を呼んで打ち合わせをしています。逆に、私が呼び出されるときはいつもドキドキしてしまいます。なぜならば、辞表を言い渡されることが過去に何度もあるからです。話は変わりますが、会議がないせいか、雑談の中で気が付くと税務の相談をしているケースが多いです。なので、柔道着のあげるあげない等の仕事に全く関係ない話が仮に耳に入ったとしても、それを咎めようとは全く思いません。自由な職場の方が意見の交換も活発に行われるだろうからです。老子のことばに『大国を治むるは、小鮮を烹るが若し』というものがあり、私がとても好きな言葉です。あまり細かな指示を出し過ぎないほうが組織はうまくまわると思います。茨城本部では、若返りも兼ねて若手職員の採用を積極的に進めています。若手職員は失敗や反省をしながらも、先輩社員に感謝の気持ちをもって接しています。先輩社員も長い目でみて優しく、ときに厳しく指導してくれています。若手社員から「感謝」ということばがでることがわたしはうれしいし、私自身も指導してくれている先輩社員に心から感謝しています。職場において、「皆さんの給料の源泉を考えよう、そして、顧問先に感謝をし、十分に御満足いただけるサービスを提供しよう」と話しています。同じ価値観を共有できる仲間がいること、そのことを糧に現状の苦しい局面を乗り越えていけたらうれしいなと思います。
茨城本部 楢原 英治
新型コロナウィルスの感染拡大を受けて緊急事態宣言が2020年4月8日に発令されました。それを受けて当税理士法人も緊急融資の為の月次試算表作りや支援策等の相談業務に追われております。
そこで新型コロナウイルス緊急経営支援策一覧を作成しました。内容についてはURLをクリックしてご確認ください(4月9日現在)。
1 国・都道府県等の支援策 4月13日20:00時点版の経済産業省はこちら ↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
2 相談窓口
Ⅰ 雇用の維持
Ⅱ 資金繰り支援
Ⅲ 税制面等の支援
1.国・政府系金融機関の支援策
経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」
新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策が案内されています。
「支援策パンフレット」に、官公庁横断での支援策がまとまっています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
2.都道府県・市町村の支援策はこちら
J-Net21(運営:中小企業基盤整備機構)に、都道府県別の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています。
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html
こちらも県別検索出来て便利です。→ https://covid19.moneyforward.com/
1.経済産業省「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」
日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
日本政策金融公庫等が、3月17日(火)から新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方向けの融資制度「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取り扱いを開始。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
【Ⅰ雇用の維持】
1.厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
2.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
3.委託を受けて個人で仕事をする方向けのコロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
4.厚生年金保険料等の猶予制度
file:///C:/Users/watan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/N5QLEUXP/10.pdf
5.時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html
6.厚生労働省「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」
7.厚生労働省「時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
沖縄振興開発金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
https://www.okinawakouko.go.jp/3748
商工中金「危機対応融資」
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)「新型コロナウイルス対策マル経」
https://tutumikaikeisample.tkcnf.com/tkc-corona
3.セーフティネット保証4号・5号
中小企業庁「セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
●セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html
●セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012.html
【Ⅲ 税制面等の支援】 当優和税理士法人の[新型コロナウィルスへの申告や納税などの当面の税務上の取扱い](2020年04月03日)をご覧ください。https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174597/
東京本部 渡辺俊之
新型コロナウイルスの感染拡大により事業にも大きく影響が出てきている方も多いかと思います。それによりただちに納税をするのが困難な場合には換価猶予の申請を行うことができる可能性があります。換価の猶予を受けた場合には、分割して納付することとなります。延滞税も発生しますが、申請せずにいる場合とでは年率も変わるため提出した方が有利となります。
換価の猶予の要件としては以下となり、その全てを満たす必要があります。
イ 納付すべき国税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を
困難にするおそれがあると認められること。
ロ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。
ハ 滞納者から納付すべき国税の納期限から6月以内に換価の猶予の申請書が提出されていること。※1
ニ 納付すべき国税について納税の猶予の適用を受けている場合でないこと。
ホ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税以外の国税の滞納がないこと。
ヘ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税の額に相当する担保の提供があること。※2
※1 場合によっては税務署長の職権により認められる場合もあります。
※2 以下の場合は担保の提供不要となります。
① 猶予を受ける金額(未確定の延滞税を含みます。 )が 100 万円以下である場合
② 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
③ 担保を提供することができない特別の事情がある場合
【猶予の期間】
換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。
現在、国会で審議されている納税猶予の案では令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する、所得税・法⼈税・消費税などの税金を事業等に係る収⼊が前年同期に比べておおむね20%以上減少している方に限り延滞税を免除するという話が出ております。
納税猶予について知りたい方は最寄りの税務署または税理士法人優和までご連絡ください。
京都本部 近藤