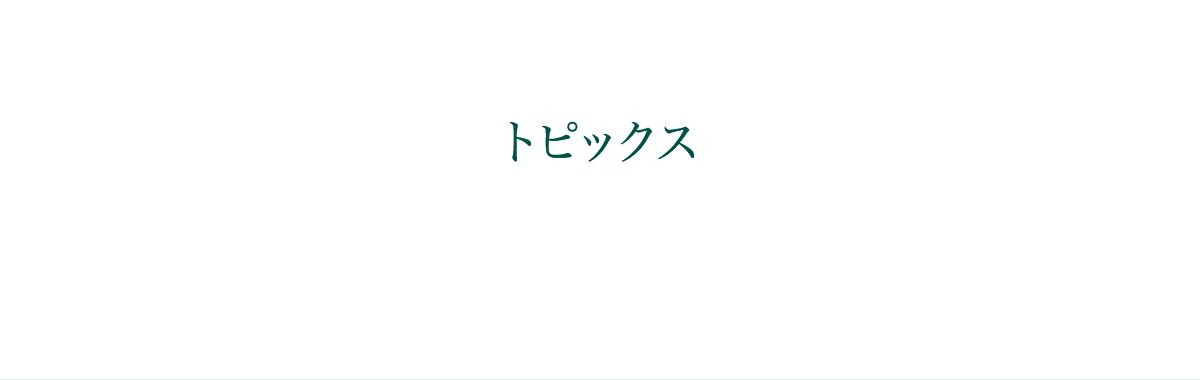
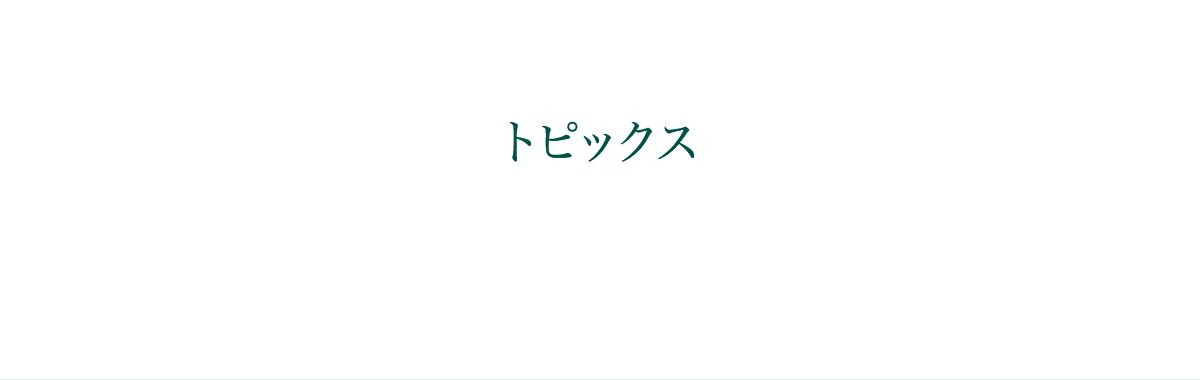
◆ネットジャーナル
「モノ不況」と世界経済の底堅さ
消費者物価(全国23年7月)
~補助率縮小に、円安、原油高が重なり、
ガソリン、灯油価格は8月以降に大幅上昇へ
◆経営TOPICS
令和4年
雇用動向調査結果の概況
◆経営情報レポート
厳しい経営環境を乗り越える
中小企業の経営強化のポイント
◆経営データベース
中期経営計画のメリット
中期経営計画策定の第一歩
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/08/k836.pdf
◆医療情報ヘッドライン
重症度、医療・看護必要度見直しへ
高齢者の救急搬送の多さを問題視
医師が常駐しないオンライン診療所
開設は「準無医地区」に限定
◆週刊 医療情報
暗証番号なしでマイナカード交付へ
◆経営TOPICS
介護保険事業状況報告(暫定)
(令和5年3月分)
◆経営情報レポート
ネット上の迷惑行為に対抗する
SNSによるトラブル防止策
◆経営データベース
一人医師医療法人制度とは
基金拠出型医療法人について
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/08/i785.pdf
◆未来投資を始める企業が増えてきた
◆父は敬の対象、母は愛の対象
◆ベトナムの「日本離れ」
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/08/k1321.pdf
住民税、自動車税、固定資産税、不動産取得税など新たにキャッシュレスによる納税が可能になりました。
今までは納税のためにコンビニや銀行まで支払いに行くなど面倒な手間がかかっていたことでしょう。
この納税方法が・・・な、ななな何と!お家にいながらスマホの操作だけで出来ちゃうんです!
方法は簡単。
納付書に記載されているQRコード「eL-QR」をスキャンして読み取れば自動的にキャッシュレスによる納付画面に移動するので金額を設定すれば簡単に誰でも納付できます。
しかし、普通にやっては残念ながら1%のポイントはもらえません( ;∀;)
では、どうする諸君
おすすめは楽天ペイでチャージして納税する方法です。
楽天ペイは楽天カード等からのチャージ機能があります。チャージをすることでまずチャージ金額の0.5%の楽天ポイントがもらえます。
毎月1のつく日(1日、11日、21日、31日)にチャージをすると(事前エントリー必須)+0.5%の楽天ポイントがもらえちゃうんです。
この方法を使えば納税額の1%をgetできます。
1%・・・されど1パーセントです。結構デカいです。
税金の種類によってはもらったポイントでガソリン代くらい賄えます。
ガソリン代の高騰で財布が寂しいと仰るそこのあなた、値上がりラッシュでイライラを抑えきれないあなた。もらったポイントで懐を温かくしてみませんか?
(注意点:一回の納付上限は30万円までです。)
余談ですが、、、楽天ペイではポイント(期間限定ポイント含む)での納税も可能です。
明日期限を迎える予定のポイントで税金が払えちゃうんですよ。
最近はポイントラッシュと思えるほどポイントセールがたくさんあります。
是非一度試してみてはいかがですか?
人生観が変わるはずです!!!
知らんけど、、、、、
茨城本部 大河原
◆ネットジャーナル
注目される「需給ギャップ」の
利用上の注意点
企業物価指数(2023年6月)
~輸入物価の下落が進む
◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和5年5月実績)
◆経営情報レポート
働きやすい職場環境をつくる
中小企業が取り組むべきハラスメント防止策
◆経営データベース
ナレッジマネジメントと文書管理の違い
ナレッジマネジメントの「暗黙知と形式知」について
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/k832.pdf
◆医療情報ヘッドライン
自治体病院23%が宿日直許可未取得
現状は「許可を取りたくても取れない」
紹介事業者の認定基準を厳格化
半年以内の離職は手数料を返戻
◆週刊 医療情報
医療法人の経営データ、
地域別集計など検討へ
◆経営TOPICS
介護保険事業状況報告(暫定)
(令和5年2月分)
◆経営情報レポート
マイナカードと健康保険証の一体化!
オンライン資格確認とレセコンの活用法
◆経営データベース
腰部に関する労災認定について
通勤途中に怪我をした場合の認定
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/i781.pdf
◆働き手はフラットな組織に引かれ始めている
◆「お天道様」は見ている
◆セブン&アイ売上高10兆突破でも消えない不安
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/97f8af133e22ef3a87a084f32725b84f.pdf
いろいろなお客様とお話する中で最近よく聞くのが「土地なんか持ってても大変なだけで何のいいこともない、ほっといても草刈はしなくてはならないし、本当に困る、売れても二束三文だしまさに負動産だ!」と嘆かれる方が多いように感じます。
確かに首都圏の交通の便の良い土地ならまだしも、建物の建築制限が厳しい地方の市街化調整区域や高齢化で耕作人がいない農地などは、なかなか買手がつかないといいます。維持費や固定資産税ばかりがかかるので手放したいと考える方も増えているでしょう。このような土地を相続を契機に取得した場合、取得者の負担感が増加し管理の不全化も招いてしまいます。
そこで相続した土地を手放したいと考える方の新たな選択肢として相続土地国庫帰属制度が創設され令和5年4月27日から施行されました。
これは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能にする制度です。
国庫に帰属した土地は、普通財産として国が管理・処分し、主に農用地として利用されている土地、主に森林として利用されている土地は農林水産大臣が管理・処分し、それ以外の土地については財務大臣が管理処分します。
要件は、
①通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地は対象外
具体的には、建物の存する土地、担保権や使用収益の権利が設定されている土地、墓地、境内、通路等などの用に供されている土地、特定有害物質に汚染されている土地、境界等争いのある土地は申請しても却下されます。
また、勾配が30度以上であり、かつ、高さが5m以上の崖がある土地、土砂崩落など災害に発生防止のための措置が必要な土地等も不承認要件として挙げられております。
②土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費用相当額の負担金の納付が必要、審査に要する実費として審査手数料の納付も必要です。
負担金算定の具体例として、宅地、田畑は面積にかかわらず一筆20万円、ただし一部の市街地の宅地については面積に応じて算定されます。(例100㎡ 約55万円、200㎡ 約80万円)同様に一部の市街地、農用地区域等の田畑についても面積に応じて算定されます。(例500㎡ 約72万円、1,000㎡ 約110万円)また、森林は面積に応じ算定され、例として1,500㎡ 約27万円、3,000㎡ 約30万円となります。
この制度を利用するにあたり、デメリットとしては家が建ってる場合は国庫に帰属できないため、更地にしなくてはならずそのための家の解体費用がかかる、境界が明らかでなければ測量が必要となるなど管理費用以外の金銭的な負担があります。
いずれにしましても固定資産税を払いながら管理を続けていくか、または金銭的な負担はあるがその管理から解放されるか、メリットデメリットを勘案して、この制度の利用の可否を考えていく必要があるでしょう。
埼玉本部 瀬島 通予
◆医療情報ヘッドライン
セキュリティ対策のチェックリスト
「確認の実行性を高めるため」公表
特定行為研修受講にインセンティブを
医師の働き方改革でタスクシフト促進
◆週刊 医療情報
社会保険負担を歳出改革で軽減、
骨太方針決定
◆経営TOPICS
介護保険事業状況報告(暫定)
(令和5年1月分)
◆経営情報レポート
万が一の事故に備える
医療事故調査制度の概要
◆経営データベース
200床規模の病院の経営強化策
専門病院の差別化戦略
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/i777.pdf
◆ネットジャーナル
【アジア・新興国】東南アジア経済の見通し
~輸出低迷により景気減速も、インフレ沈静化で内需主導の底堅い成長へ
米住宅着工・許可件数(23年5月)
~着工件数は前月、市場予想を大幅に上回る
◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和5年4月実績)
◆経営情報レポート
人事部門の抱える課題を解決する
ピープルアナリティクス導入のポイント
◆経営データベース
残業時間を代休に振替える場合
フレックスタイム制の労使協定
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/k828.pdf