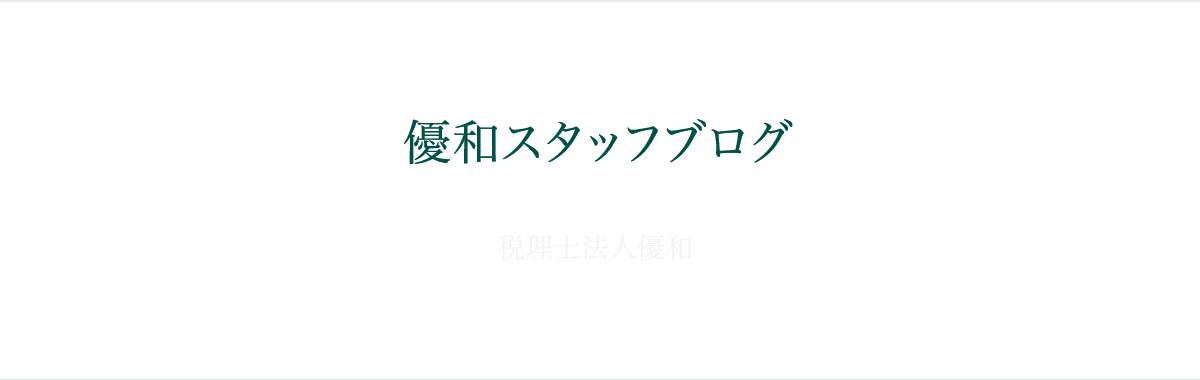
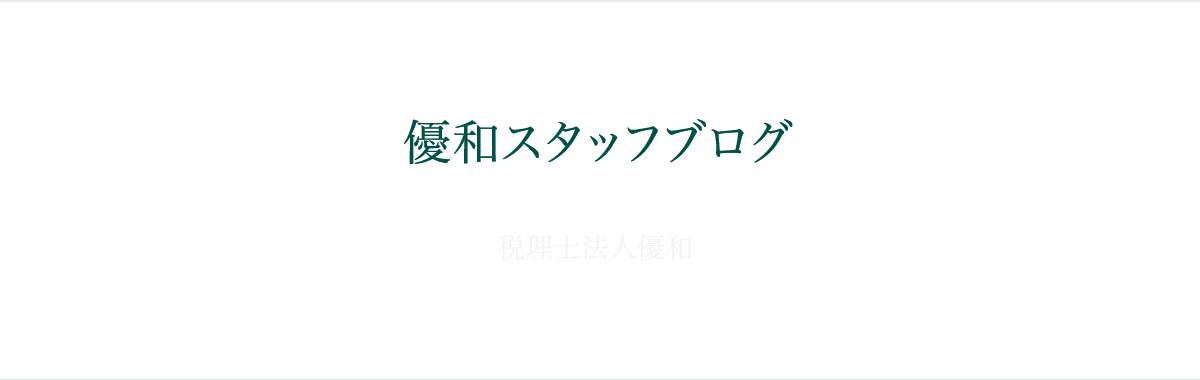
坂の上の雲ミュジアム
前回で少し紹介しましたが、坂の上の雲ミュージアムが、平成19年4月28日開館しました。
このミュージアムは松山のまち全体をフィールドミュージアムとする構想の一角を担う施設として創立されました。地下1階、地上4階建てで、建築家 安藤忠雄氏による設計のもと平成16年12月22日着工、平成18年11月30日に竣工しました。
松山城周辺の歴史や文化を意識して考えられた建物は周囲の自然環境に配慮した外観と安藤氏がイメージする「坂の上の雲」を表現した空間となっています。
観光客からはよく、ミュージアムはどこかと尋ねられることがあると聞きますが、入場者数は当初の予想・計画を大幅に上回っているようです。
今年の秋から来年以降、ドラマの撮影が始まると一層、松山が全国的に知られてくると思いますが、独自の文化を維持しつつ、新しい松山が発見できることを期待しています。
ドラマといえば、「バルトの楽園」という映画がありますが、この物語は、第一次世界大戦中の徳島県鳴門市の板東俘虜収容所で起きた実話を基に、収容所所長・松江豊寿の活躍や、俘虜となったドイツ兵と地元の住民の交流などを描いた感動の映画です。
その十年前の1904年(明治37年)に始まった、大日本帝国とロシア帝国が、朝鮮半島と満州の覇権を巡って争った日露戦争を背景に描かれたのが、司馬遼太郎作「坂の上の雲」です。
この日露戦争の時に捕虜となったロシア兵のうち、松山俘虜収容所には延べ6,000人余りが収容されました。病気や戦場での傷が元で命を落とした98名のロシア兵士達の安らかな眠りを願って、立派なロシア人墓地がたてられました。
(次回はこの松山俘虜収容所を紹介する予定です。)
松山本部 村上
やっと暖かくなってきたので、そろそろ我が家では恒例の「名水汲み」
にいく頃となりました。
埼玉県で有名な名水といえば、寄居町の「日本水(やまとみず)」です。
古くより干ばつ時、雨乞いのもらい水で御利益がある霊水として広く崇められていて、
環境省の「名水百選」にも選ばれています。私達は「日本水」から、さらに西の秩父
まで足をのばして、車で山を登っていきます。
きっかけは友人からの情報でした。始めは「そんなに水道水と違うのか?」
と半信半疑でしたが、実際行ってみると、水が湧き出ている取水所で
順番待ちをしていて、また県外からも水を汲みにきている方もいて驚きました。
そんな湧き水を飲んでみた感想は「やはり混じりけのない純水」でした。
それからは、なくてはならない「生命の源」(ちょっと大袈裟?)となり、2??3ヶ月に
一度、18リットルの水用タンクを10ケほど積んでドライブがてら、いろんなお店に
寄り道をしながら、湧き水を汲みに行くようになりました。
(余談ですが水タンク専用収納棚を特注してしまいました・・・)
皆さんにも、こんな「”めんどくさい”こだわり」はありますか?
埼玉本部 武井
我が家では妻の前厄から始まって今年の私の後厄まで6年、厄年が続いています。
この間、何かあったわけでもないですが、「当たらずしも遠からず」のような状態にはあります。
個人的には厄年は非常に長い期間、多数のサンプルをとった統計のようなものと考えていますが、年初にお祓いは欠かしておりません。
さて、ここ京都において厄除けで有名な神社仏閣の一つに「壬生寺」があります。
全国的には新撰組関連施設として名前が通っているかもしれませんが、節分には吉田神社と並んで参詣者で賑わう場所です。
この壬生寺には重要無形民俗文化財である「壬生狂言」が伝承されており4月21日から9日間、春の公開が始まります。元々は仏教説話を無言劇に仕立てたものだそうです。
公開期間はゴールデンウィークの前半と重なります。能の演目などもありますので興味のある方は足を運ばれてはいかがでしょうか?
壬生寺
http://www.kyoto.zaq.ne.jp/mibu/
壬生狂言
http://www.kyoto.zaq.ne.jp/mibu/kyougen.htm
4月の壬生狂言公開
http://www.kyoto.zaq.ne.jp/mibu/k_annai.htm
旬の京都情報:JR東海
http://kyoto.jr-central.co.jp/
京都本部 二神幸彦
3月5日の真夜中、ウ??カンカンウ??カンカンと騒がしい音がするので
どこかで火事があったのかなと思いつつ起きてみると、どんどん消防車
のサイレンが迫ってきました。
慌てて家を飛び出してみると、50メートル先の家が火柱を出して燃え
ているではありませんか。大声で家族に知らせて現場に近づくとすでに
消防隊員が20名ほど消火活動をされていました。
1時間も燃え続けて家は全焼となりましたが、住んでおられた老夫婦は
重傷でしたが命は助かったそうです。
今迄に何度か火事は見た事がありましたが、これほど近所の火事は経験
がありません。現在も焼け跡が残っているので毎日思い出します。
災害の恐ろしさを痛感した真夜中でした。
京都本部 田村
坂の上の雲まちづくり
「坂の上の雲」ドラマ化!
司馬遼太郎の代表的長編小説。この小説を原作として、NHKスペシャルドラマが平成21年(2009年)から3年にわたって放送されます。
物語は、松山出身の正岡子規、秋山好古・真之兄弟の3人の人生を辿りながら「近代国家」の仲間入りをしようとした明治の日本を描いています。
彼ら3人が、松山で生まれ、育ち、そして上京し、子規は文学、俳句の道、好古は陸軍、真之は海軍と、それぞれの持ち場で、日露戦争が勃発する激動の時代をひたむきに駆け抜けていく姿が描かれています。
そして主人公3人が抱いた高い志とひたむきな努力、夢や希望をまちづくりに取り入れたのが、「坂の上の雲」のまちづくりです。松山城をはじめ、市内には小説ゆかりの遺産が各地に残り、または眠っています。それらを行政と市民が一緒に見つけ、活用し、一体となってまちを元気にしていこうとするものです。官民一体となって、「物語り」が感じられるまちを目指す、それが全国ではじめて取り組む「小説を活かしたまちづくり」です。
これから、まちづくりが進んでいく上で次回から進捗を報告できたらと思っています。
ちなみにNHKでは平成19年秋から撮影開始に入る予定です。
主な出演者と役柄は
秋山 真之(あきやま さねゆき)・・・本木 雅弘
秋山 好古(あきやま よしふる)・・・阿部 寛
正岡 子規(まさおか しき)・・・・・香川 照之
正岡 律(まさおか りつ)・・・・・・菅野 美穂
(松山市HP参照)
松山本部 村上
東京は2月11日まで雪のない冬で、47年ぶりの新記録だそうです。
我が家(東京港区三田)の隣の桜はすでに満開に近いです。まるで春真っ盛りのように小鳥がたくさん
囀っています。
もともと早咲き桜ですが、この時期に満開とは珍しいので写真を掲載しておきます。
東京本部 渡辺俊之
埼玉本部から初エントリーです。
これから順次エントリーしていきますので、よろしくお願いします。
埼玉本部のメンバーの自己紹介
http://www.iino-kaikei.com/jimushoshoukai/syokuin.htm
埼玉県蓮田市は、東京から北北東約40KMに位置します。
JR宇都宮線を利用すると東京駅、新宿駅それぞれ約1時間といった距離感です。
特段便が良いというところではありませんが、さいたま市と隣接しており、さいたま市の郊外と比べればかえって都心へのアクセスは便利かもしれません。
高層の建物が少ないため、事務所から富士山や秩父連山が、周辺へ出れば筑波山、日光連山、赤城山、冬には雪化粧した浅間山の眺望が楽しめます。
そんな平々凡々とした地域から、気楽にエントリーしていきます。
埼玉本部 飯野浩一
11月末に、京都本部から歩いて5分程の場所に、「京都国際マンガミュージアム」という世界初の
マンガの博物館がオープンしました!
このミュージアムは、京都市と京都精華大学との共同事業により、閉校された元龍池小学校を
改装し作られました。 日本のマンガ・アニメーションは、国際的に高い評価を得ており、
また、国内でもサブカルチャーではなく、芸術分野のひとつとして位置づけられつつあります。
平安時代の絵巻物語から始まる日本のマンガ文化を研究することや、生涯学習・地域の活性化等
を目的として作られたそうです・・・。
さっそく私は、小学3年生の息子と一緒に行ってみました??。
マンガが大好きで育った私にはとても楽しかった・・・そして、懐かしかったです。
ドラえもん は勿論のこと、最近のNANAやワンピース、そして世界のアニメなど約20万部を自由に
観覧することができ、子供と目をキラキラさせながら夢中で読んでいました。。。
懐かしさの理由は、もう一点ありまして・・・この小学校は私の母校なのです。
私が通っていた頃でも創立110年は経っていた小学校です。歴史があるので、放課後うす暗くなると
幽霊(!?)がでてきそうで怖かった想い出があります。すっかり明るくキレイになりましたが、
階段などは昔の面影があり、いろいろな想い出が蘇えり懐かしさで胸がいっぱいになりました。
そして、私の原点でもあるこの場所で、現役小学生の自分の子供と一緒にのんびりと過ごせている
ことに幸せを感じたのでした!
カフェもあり、人工芝の運動場で遊ぶことも出来ますよ。 !(^^)!
お時間があればぜひぜひ行ってみてください♪♪
HPはこちらです → http://www.kyotomm.com/
京都本部 山室道子
「松山や秋より高し天守閣」
この俳句は正岡子規が松山城を詠んだ俳句ですが、松山という名前は1602年(慶長7年)正月15日を吉日として、加藤嘉明(豊臣秀吉と柴田勝家との戦いで活躍した「賤ケ岳の七本槍」の一人)が道後平野の中央に位置する勝山に築城の工を起こし、山の名前を松山と改めたことに始まります。そして1月15日を松山城誕生記念日として毎年この日は無料開放をしています。
松山人にとっては日常であり幻視でもありますが、夜ふっと息を抜いて星の高さに目をやる時、その視界のどこかに必ず松山城が像を浮かべています。松山のどこからでも見ることの出来る位置にはちょっとした嘉明の思いがあり、築城候補地として、天山、勝山、御幸寺山を徳川家に上申し、勝山に築城の許可を得ています。しかし勝山は、第二候補地でした。当時、徳川家は築城地に第二候補地を選ぶことが多く、嘉明は、希望の勝山を敢えて二番目の候補地として申請したのです。事は嘉明の思い通りに進み、勝山への築城となったのです。
松山城は1627年(寛永4年)に、25年の歳月をかけて完成しました。築城当時の天守閣は五層でしたが、その後、三層へと改築(天守閣の規模が大きすぎるので幕府に遠慮したためという説と、二つに分かれていた峰を切り崩し埋めた、もともとは谷の位置に天守閣があったため地盤が不安定なので安全を考えたという説とがあります。)されています。
その後、天守閣は落雷で焼失したため、約150年前の江戸末期に再建されました。現在の建物は、昔の姿のままの総木造となっており、わが国城郭建築史上における最後の作品として注目されているそうです。
なお、平成16年10月から約2年間にわたり、行われていた国の重要文化財の天守閣など7棟の保存修理工事が平成18年11月に完了しました。松山城には50棟の建造物があり、そのうち21棟が国の重文に指定されています。
これからも松山市のシンボルとして市民や観光客に親しまれていくことでしょう。
(松山市HP参照)
松山本部 村上
皆様は「京の名工展」をご存知でしょうか?
京都府では、永年に渡り伝統産業に従事し、優れた技術をもってその発展に寄与されてきた名工の方々の作品を集めた展覧会を実施しています。
昭和36年度から毎年開催され、今年は10月末に開催されました。
実際に京の名工の方からの薦めもあり、今年初めて行ってきました。
会場内は、刺繍・織物・扇子・印刻・陶磁器・京人形など100点以上の京都らしい作品に満ち溢れており、想像していたよりもずっと多くの人々が食い入るように作品を見ていました。(写真撮影不可の為、皆様にお伝え出来ないのが残念です。)
そこで感じたのは、名工の方々の作品に対する熱い思いでした。
なかには、作品の説明をして下さる名工の方もいて、京都の伝統産業に直に触れ、非常に有意義な時間を過ごすことが出来ました。
正直なところ、今まで私はこのような展覧会にあまり参加したことがなかったのですが、そんな人間でも、今回の経験でもっと京都や日本の歴史を知りたいと感じるようになりました。
是非、皆様も来年の「京の名工展」に足を運んでみられてはいかかでしょうか。会場を後にする時には、この気持ちを誰かに伝えたい、そんな思いでいっぱいになることでしょう。
京都本部 大林