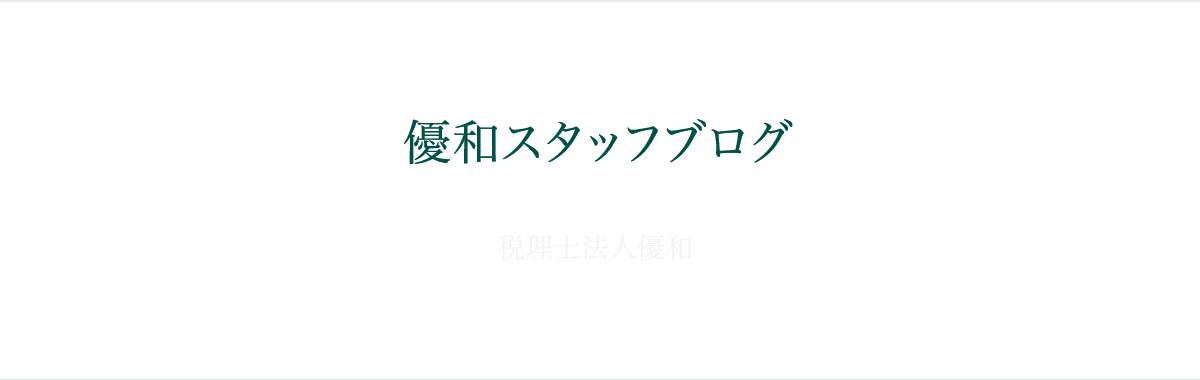
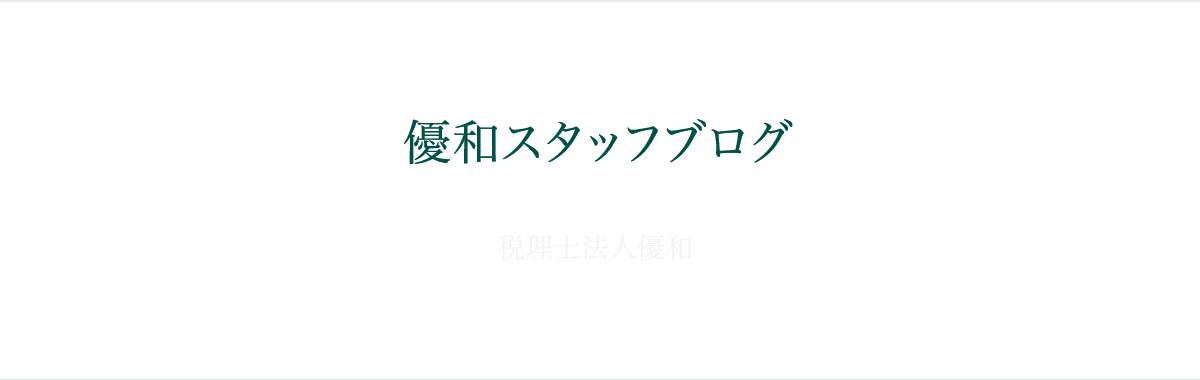
最近本屋さんで見つけて、ついつい買ってしまった本に「いつのまにか変わってる地理・歴史の教科書」という本があります。これは新しい発見や学説により中学校・高校の歴史や地理の教科書の内容や表示が時代とともに変わってしまっている部分が結構あるというもので、たとえば聖徳太子なんかは今の教科書では厩戸皇子と表示されいるとのことです。
また私が学生の時には当り前のように載っていた歴史上の人物の肖像画も実は別人ということが最近分ってきた例が多く、源頼朝や足利尊氏、武田信玄は別人ということで今の教科書ではそれらの肖像画はほとんど出てこなくなっているようです。(教科書ではまだ本人として載っているようですが西郷隆盛としてよく出てくる肖像画も実は弟の従道をモデルとしたもので随分本人とイメージが違うようです。そういえば前に幕末維新の志士が一同に会した写真を見たことがありますが西郷といわれている人物はチェ・ホンマンそっくりでした。)
話はそれますが戦国時代に登場する豊臣秀吉の子、秀頼や小早川秀秋の現在残る肖像画を見たことがあるでしょうか?両者とも、ひ弱そうな情けない感じで描かれています。でも実際の秀頼は恰幅がいい武者という記述もありますし、小早川についても少なくとも一軍の将だったわけですからそれなりの武将だったのではないでしょうか。しかし前者は時の権力者である徳川の時代に描かれたものが多く、後者は裏切り者のイメージが強いため、あのような感じになってしまったのでしょう。しかしながら歴史小説を読んでいて両者が出てくるとどうしても肖像画のイメージを思い浮かべて読んでしまいます。普段人と接する時もついつい最初についたイメージでいつまでも接してしまうことがありますが気を付けたいものですね。
京都本部 古吉
先日、京都市営バス(以下、市バス)に乗っておりますと、停留所で待っていた観光で来られた風の若い二人連れの方が、『スゴイ~!』と大声で叫んでおられました。
何がスゴイのか、と見てみると、バスの左側(乗降車側)が上下運動することに驚かれている様子です。乗客が乗り降りしやすいためのものですが、このような工夫や新しい試みは、大歓迎です。京都の市バスは、使用済天ぷら油で走らせたり、100円循環バスの運行、バスロケーションシステムの設置などの乗客にとっては、有難い取り組みをされています。紅葉で染まる京都は1年で最も良いシーズンです。市バスで京都観光されてはいかがでしょうか。
京都本部 T.K
マレーシアの旅行と聞き、一番に頭に浮んだことは、マレーの虎ハリマオだった。
私が11歳の頃、日本テレビ系で怪傑ハリマオが放映された。日本初のカラーテレビでもある。強烈な印象を受けた。
実在の人物らしい、名前は谷 豊、昭和初期にマレー半島で活動した盗賊で、のちに日本陸軍の諜報員となった。
写真はペナン島で撮影したものです。
快傑ハリマオの歌
1 まっかな太陽 燃えている
果てない南の 大空に
とどろきわたる 雄叫びは
正しい者に 味方する
ハリマオ ハリマオ
ぼくらの ハリマ






tom
我が家の小五の次女が全国染織連合会主催の「全国きものデザ
インコンクール」ジュニアの部で2年連続佳作をいただきました。
応募作の中から何点かが作品にされます。
昨年はテントウムシのデザインを着物にしていただき、私は単純に
喜んでいただけなのですが、自宅にテレビ局が取材に来たり、
授賞式のリハーサルがあったりと本人と妻は忙しそうでした。
今年は何を書いたのか尋ねると「蛙」と一言。
今回は作品にならないと事前の噂でしたが、帯のデザインに採用
していただけました。もしこれらの作品を譲っていただけたら、
娘たちはテントウムシ柄の着物に蛙の帯で成人式に出るのかな?
と想像してしまいました。
その前に妻が卒業式に着ていくかもしれません。
味覚狩りや紅葉狩りといった、行楽シーズンになりました。
出かける前は、天気が気になるところです。
天気予報はテレビニュースやインターネットで調べられますが、その中でも気象庁の天気予報がオススメです。
天気はもちろんのこと、降水確率や気温の他に、「信頼度」というものが表示されます。
「信頼度」とは”予報が的中しやすいかどうか”を、A、B、Cの三段階で表したものです。
週間天気予報を見ると、このA、B、Cが表示されますが、現在に近いほどA評価であるとは限らず、
A評価の次の日はC評価でその次の日はA評価・・と少しハラハラさせられます。
先日、屋外のイベント会場で知り合った方と「晴れてよかった」と話をしたところ、
この方も同じく気象庁の天気予報を見ていたそうです。
「信頼度が低くて心配した。」と、お互い思わず笑ってしまいました。
皆さんもお出かけの前には、天気予報を活用してみて下さい。
京都本部 村上
10/5~10/7にかけて、松山市では秋祭りが開催されました。 松山市の伝統行事で、10/7は祭日の所が多く、学校や地元の企業は休日になります。 私達は通常勤務でしたが。。
神輿が色々な所に出没し、車よりも優先して道路を使用するので、通勤や仕事の訪問に多少影響がありました。子供神輿や女神輿がありますが、やはり迫力があるのは、神輿同士をぶつけあう“鉢合わせ”です。今年は、数人のけが人が出たみたいですが、過去には死者も出てしまい、ある意味命がかかっています。
お祭りは気分が高揚してしまいますが、マナーをもって楽しみたいものですね。
松山本部 松浦
秋。ツーリングするにはもってこいの季節です。
最近、大学のときに二輪の免許を取って以来、乗っていなかったバイクに久々に乗りました。
レンタルで選んだバイクが、ヤマハのDragStar(ドラグスター)。教習所のバイクとはタイプが違うので少し戸惑いはありましたが、なんとか走らせることができました。
9月末に美山方面へツーリングに行ったのですが、田舎風景がきれいで、緑や川のせせらぎに耳を傾け、ゆっくりとした時間を過ごすことができました。
さらにこの時期ならではの彼岸花が鮮やかに咲いていて、こころ弾むひとときでした。
もう少しすると京都も紅葉してきます。今年は例年通り11月中旬が見ごろのようです。
市内に住んでいると自然に触れ合うことが少ないですが、こうして季節の花を見たり、景色の中に身を置くのもたまにはいいなぁと思いました。
またツーリング企画に参加して紅葉狩りに行きたいなぁと思っております。
京都本部 藤岡
平安時代の宮中の歌会遊びを再現した「曲水の宴」が11月3日、
京都市伏見区の城南宮で行われます。
曲水の宴は古代に中国から伝わった宮中行事で、庭園を流れる
小川に沿って歌人が座り、水鳥をかたどった台に載せた酒杯が
流れてくるまでに、即興で和歌を詠み、杯を飲み干す遊びです。
琴の音が鳴る中、色鮮やかな狩衣と小袿(こうちぎ)をまとった
男女7人が短冊に筆を走らせ、酒杯を口にしていきます。
城南宮では春と秋の2回、曲水の宴を無料公開しており、沢山の
見物客で賑わいます。
それ以外の時は、源氏物語にちなんだ植物が数多く植えられて
いる神苑が有料で公開されています。
普段は人がそれほど多くなく、ゆっくりと様々な植物を楽しむ事が
できるのでおすすめですよ。
京都本部 今尾
2年続けて総理がやめたと思ったら、今度は小泉純一郎が政界引退?
で、息子に継がせるとか。政治家とは世襲制度でしたっけ?
と疑問に感じるこのごろ
自民党をぶちこわす!構造改革を推進するといった人が最後はこれですか?
毎年、春分の日と秋分の日には実家へお墓参りに帰ります。今年の彼岸入りは9月20日、9月23日が中日、9月26日が彼岸明けでした。彼岸とは、煩悩を脱した悟りの境地のことで、煩悩や迷いに満ちたこの世をこちら側の岸「此岸」(しがん)と言うのに対して、向う側の岸「彼岸」を意味する言葉です。太陽が真東から上がって真西に沈み、昼と夜の長さが同じになる春分の日と秋分の日を挟んだ前後3日の計7日間を「彼岸」と呼び、この期間に仏様の供養をする事で極楽浄土へ行くことが出来ると考えられ、仏教行事でありながらお彼岸にお墓参りをする習慣は日本独自の行事です。私の実家では、団子を作ってお供えしますが、一般的に「ぼたもち」や「おはぎ」を、お彼岸にお供えします。両方とも、蒸した餅米とアンコの同じ素材でつくられる食べ物ですが、季節の花になぞらえて、春の彼岸にお供えするのが牡丹餅で、秋にお供えする場合はお萩と言われます。「暑さ寒さも彼岸まで」と言われているように、日本の四季の中でも最も過ごしやすい季節になります。せめてお彼岸の数日間は、御仏のおられる彼岸を思って、修行に励もうと言う、いわば仏道週間とも言えるものなのです。
京都本部 藤原