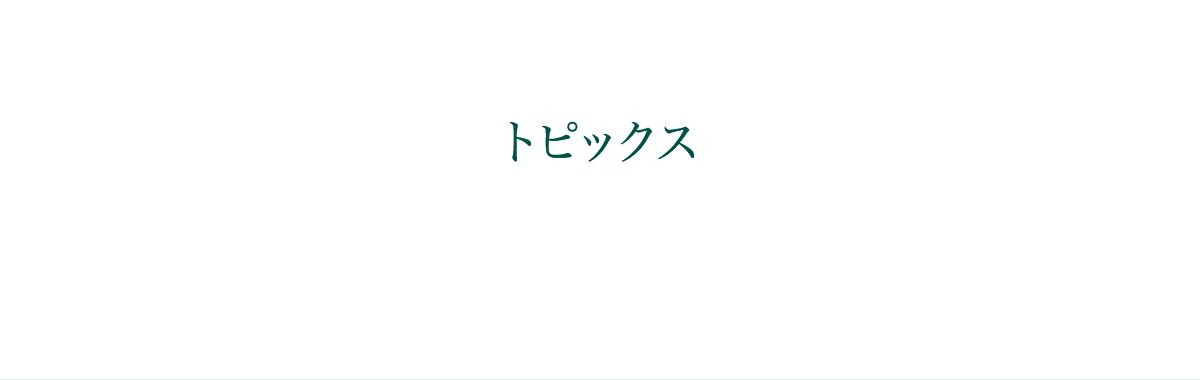
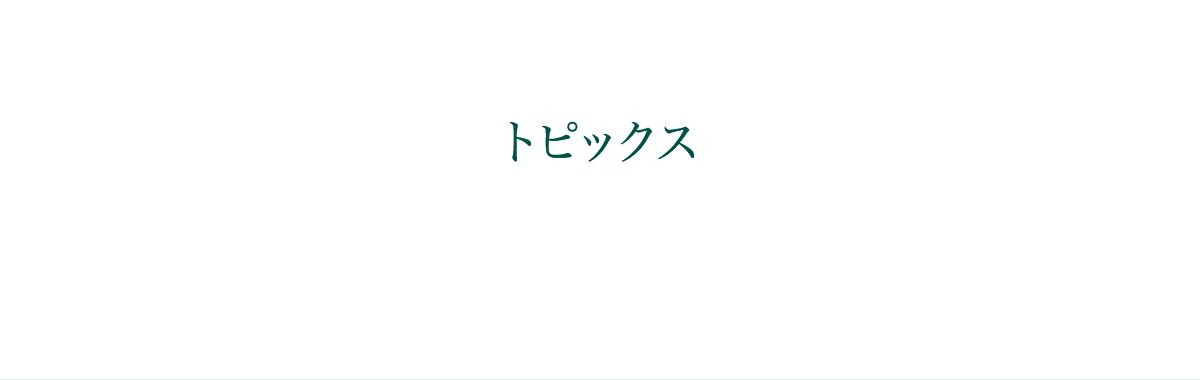
◆日本が第3集団へ転落した原因
◆成功の秘訣は「ABC+DE」
◆「14%輸送不可」を緩和できるか
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/k1345.pdf
最近日経平均株価がバブル時代を超え、過去最高を記録しました。当時、私は株など全くやってなく、その後のITバブルを少し経験した程度ですが、アメリカなどの株価を見ると、かなり時間がかかったなというのが率直な感想です。
今年から新NISAも始まり、投資環境は良くなっているとは思いますが、やはり投資は自己責任になるので、私も勉強しながら進めていこうと思います。
東京本部 木村
マイナンバーカードを利用することにより、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、スマホでも比較的簡単に確定申告を行うことが出来ます。
令和5年分確定申告から、マイナポータルアプリとの連携により、申告書の自動入力対象が拡大しました。それにより、今までは「公的年金等の源泉徴収票」「株式の特定口座」「医療費」「ふるさと納税」「生命保険」「地震保険」「社会保険(国民年金保険料)」「住宅ローン控除関係」が自動入力対象となっていましたが、新たに「給与所得の源泉徴収票」「社会保険(国民年金基金掛金)」「iDeCo」「小規模事業共済掛金」が対象となりました。給与所得の源泉徴収票の自動入力に関しては、勤め先が税務署にe-Taxで給与所得の源泉徴収票を提出していることが必須となりますが、そうでない場合でもカメラの読み取り機能等を使用することにより、自動入力が行われます。
実際にスマホでマイナンバーカードを使用して確定申告を行ってみましたが、大体1時間半程度で確定申告を終えることが出来ました。マイナポータルアプリとe-Taxの登録を行っていれば、より早く終えることが出来ていたのではないかと感じました。
転職や副業など様々なことを理由に、今までしていないかった確定申告を自身で行う必要があるかたもいらっしゃるかと思われますが、マイナンバーカードを使用することにより、自宅でも確定申告を行うことが可能となります。
確定申告期間は2月16日(金)から3月15日(金)までです。申告期間に入っておりますので、直前に焦ることのないよう早めに申告を行うようにしましょう。
令和5年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に!|国税庁 (nta.go.jp)
京都本部 石原
会計検査院が昨年11月に公表した令和4年度決算検査報告によると、退職手当等の支払を受けた者が所得税の確定申告を行った際に、退職所得の金額の加算が漏れ、基礎控除等が適正に適用されていないケースが相当数見受けられたといいます。
国税庁はHPで、退職所得の受給に関する申告書を提出した者でも、確定申告書を提出する場合には退職所得の金額を含めて申告する必要があることを明示し、注意喚起を行っております。
退職手当等の支払を受ける者は、退職手当等の支払を受ける際に所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない者が退職金等の支払金額の20.42%で源泉徴収されたものについて精算を行う場合や、医療費控除など一定の控除を適用する場合は、退職所得の金額を含めて記載した所得税申告書を提出して確定申告を行うことになります。
合計所得金額から差し引く基礎控除の金額は次のとおり。合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除額は消失する仕組みとなっております。
| 【参考】基礎控除 | |
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
| 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
会計検査院は、国税庁から所得税申告書データ及び源泉徴収票データを受けるなどして、法人の役員等に係る令和2年分又は3年分の退職所得の源泉徴収票において500万円以上の退職手当等の支払を受けたとされている者の中から、その年分の所得税の確定申告を行っていた役員等計32,843人を選定して検査しました。
検査の結果、対象者の72%(23,750人)が退職所得の金額を含めずに確定申告をしていたとのこと。この退職所得の金額を加算した合計所得金額に応じて基礎控除等が適正に適用されたかを確認したところ、合計所得金額が2,500万円を超え基礎控除の適用要件を満たさないにもかかわらず基礎控除等の額を計上するなどしていた役員等は4,515人にのぼりました。
国税庁は会計検査院による指摘を受けて、退職手当等の支払を受けた役員等の所得税申告書における基礎控除等に係る申告審理を行うにあたり、源泉徴収票データを活用した具体的な事務処理手続を定め、昨年8月に事務連絡を発出して全国の税務署等に周知しました。
また、退職所得がある年分の確定申告を行う場合は所得税申告書に退職所得の金額を含める必要があることについて、同庁HPに掲載している「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」や「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」で周知を行っております。
参考資料 税務通信
埼玉本部 秋元
今年も税制改正の内容を勉強する時期になりました。初めの感想としては、色んな分野で改正があるなという印象でした。実務処理に影響がある改正も含まれているので、例年より増して関与先のお客様に丁寧にお伝えしなければいけないなと感じています。
特に今回の目玉政策(?)である所得税・個人住民税の定額減税については、給与計算を行う方であれば、6月から影響がありますので、場合によっては早めの準備が必要になります。
制度の概要としては、令和6年分の「所得税」から本人、同一生計配偶者及び扶養親族1名につきそれぞれ3万円控除し、「個人住民税」からは、本人、控除対象配偶者及び扶養親族1名につきそれぞれ1万円控除するというものになります。(細かな所得制限等がありますので、詳細はお問い合わせください)
その減税を受ける時期ですが、①給与所得者であれば6月分の給与から、②個人事業主であれば第1期(予定)納税額から、③年金受給者であれば6月以降に最初に受ける年金から、それぞれ減税が開始されます。
上記②と③の方については自動的に計算してくれますが、①の方は給与支払者が従業員ごとに細かな計算を行う必要があります。今まで手書きで給与明細書を作成しているという方も、これを機に給与ソフトを導入するという選択肢も増えてくるとは思います。
この制度の注意点としては、令和6年度の税額は最終的には年末調整や確定申告ではじめて確定するので、年度中に扶養の異動がある方等は年末調整で徴収されるということもあり得るので、そこは従業員の方にも説明が必要です。
この他、賃上げ促進税制、事業承継税制、交際費課税、M&A税制等で改正・延長が行われておりますので、詳細を確認したいということであれば、税理士法人優和までご連絡ください。
東京本部 木村
入社してから早10ヶ月が経ち確定申告の時期になりました。11月から1月にかけては日々の入力業務に加え、年末調整や法定調書等の提出など初めての業務を経験させていただきました。忙しい日々が続きますが、体調を崩さぬように頑張りたいと思います。
茨城本部 西岡
2月に入り、雪が降り気温も下がったように感じます。
弊所では在宅勤務が可能ですので、雪が降った翌日などは在宅勤務を推奨されました。私も急遽在宅勤務をさせていただいたのですが、快適に過ごすことができ雪に少し感謝しました。
事務所が都心にあるということもあり、所員には片道1時間程度かけて通勤している人も少なくありません。在宅勤務ではその通勤時間がゼロになるので、毎朝バタバタしてしまう私も、ゆっくり起床して朝ご飯を食べられます。特に睡眠時間には顕著に影響が出ます。
これから会計事務所は忙しくなり、残業時間も増えることは確実ですが、在宅勤務を上手く利用して健康維持を図りたいと思います。
東京本部/北川
2月に入り確定申告の準備を始めておられる方も多いのではないかと思います。
今回は2024年提出の令和5年分確定申告について、従来からの変更点を5つお伝えさせていただきます。
①納税地の移動、変更の届け出が不要に
令和4年度の税制改正で、納税義務者が納税地を移動または変更した場合の手続きが見直されました。
これにより、令和5年1月1日以降は、所得税や消費税の納税地を異動・変更する際の届出書の提出が不要になりました。
異動又は変更がある場合は、第1表の確定申告書の住所(居所・事業所)欄に変更後の納税地を記載すればよいこととなります。
なお、納税地の変更等をした人で、振替納税を利用していた場合は、住所欄の下の『振替継続希望』欄にチェックを忘れないようにしましょう。
②扶養控除対象の要件
令和4年分までは扶養親族が国外に居住している場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付をすることで
扶養控除や配偶者控除の対象とすることができました。令和5年からは扶養控除の要件が厳しくなり、
30歳~69歳までの国外居住親族については、原則として扶養控除の対象から外れます。
ただし、30歳~69歳までの親族であっても①留学生、②障害者、③年38万円以上の生活費等の送金を受けている者、のいずれかに該当する場合は扶養控除の対象となります。
③上場株式等の配当の申告方法の統一化
上場株式等の配当の課税方法には、確定申告不要、総合課税、申告分離課税の3つがあり、納税者が選択できます。
令和4年分までは、所得税と住民税で異なる申告方法を選択することができました。
令和5年分から、上場株式などの配当所得や譲渡所得、特定公社債などの利子所得についての課税方式が所得税と個人住民税で統一されることになり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。
④特定非常災害に係る損失の繰越期間
災害等による損失について、生活用動産の損失は雑損失としてその年の所得の金額から差し引くことができ、引ききれない場合は3年間繰り越して、翌年以後の所得から差し引くことができます。
令和5年4月以後に特定非常災害に指定された災害による損失は、5年間の繰越控除となりました。
⑤財産債務調書の提出期限の延長
10億円以上の財産のある人や、合計所得金額が2,000万円を超えている人のうち3億円以上の財産のある人は、財産と債務の明細を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。
令和4年分までは、提出期限が翌年3月15日までとなっていましたが、令和5年分以後は、提出期限が翌年6月30日(令和5年分は令和6年(2024年)6月30日)までとなります。
確定申告の時期は、「毎年2月16日~3月15日」となっております。
ぎりぎりになって焦らないよう今のうちに準備を進めておきましょう。
京都本部 秋山
今シーズンは暖冬と言われていましたが、体はその気温に対応するようにできているのか、ちゃんと寒さは感じるものです。漏れなく風邪もひきましたし。
ところが先日、私が住む関東地方でも降雪があり雪だるまの話を聞いて、ふと思い出したことがありました。
我が家の給湯器は外気温が低くなると操作画面に⛄マークが出るようになっています。このマークが出たら管の凍結防止のため湯船に水を張っておかないといけないのです。しかし、今シーズンはまだ見ていないことを思い出しました。
3カ月予報を見るとこの先も平年より高い気温で推移するようです。果たして今シーズンは我が家の⛄に会えるのか?水張りの時間分就寝時間が遅れるから億劫だった⛄。どこかで心待ちにしている自分に気づいた、そんな出来事でした。
◆ネットジャーナル
2024年は欧州も選挙イヤー
~右派ポピュリスト勢力伸長の行方
米住宅着工・許可件数(23年12月)
~着工件数は前月を下回った一方、
市場予想は上回る
◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和5年11月実績)
◆経営情報レポート
持続的な企業価値向上のための
人的資本開示のポイント
◆経営データベース
信用調査について
与信管理と貸倒れ予防対策
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/k857.pdf